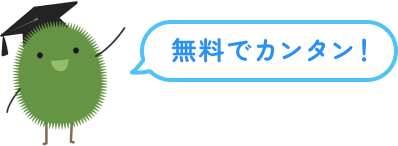【図解あり】太陽光発電の仕組みをわかりやすく解説!効率よく発電する方法、導入方法も
電気代の削減を目的に、太陽光発電の導入を検討している方は多いでしょう。しかし、そもそもなぜ太陽光を利用して発電できるのか、疑問を抱えている方もいるかもしれません。
この記事では、太陽光発電の仕組みについて、子どもでもわかりやすいように解説します。
太陽光発電とは?
太陽光発電とは、紫外線や可視光線を含む太陽光を、電気エネルギーに変換する仕組みのことです。
太陽光発電は、発電時に二酸化炭素などの温室効果ガスをほとんど排出しません。また、太陽光は枯渇しないため、持続可能なエネルギーとして、SDGsの観点からも注目されています。
【イラストで解説】太陽光発電の基本的な仕組み
太陽光発電の基本的な仕組みは、小学生でもわかるほどにシンプルです。イラストを用いて図解してみましょう。

太陽光は、屋根などに設置する太陽電池モジュールが受け取ります。機器の内部でn型半導体にマイナスの電気を帯びた電子が、p型半導体にはプラスの電気を帯びた正孔が集まります。
そこでプラス極とマイナス極が形成され、動線を通った電力が電気を生み出すのが基本的な仕組みです。
太陽光発電の仕組みをもう少し詳しく解説!
太陽光発電の仕組みについて、もう一歩踏み込んで詳しく解説します。
- なぜ光エネルギーから電気を生み出せるのか
- 発電した電気の流れ
- パワーコンディショナーや蓄電池の役割
<太陽光発電の仕組みをもう少し詳しく解説!>
それぞれを具体的に見ていきましょう。
なぜ光エネルギーから電気を生み出せるのか
太陽光発電によって生まれた光エネルギーから、電気を生み出せる理由は「光電効果」という物理現象が発生するためです。
光電効果とは、光が物質に照射された際に、物質から電子が放出される現象を指します。
光電効果を解明したアインシュタインは、この功績によりノーベル物理学賞を受賞しました。
太陽光を受け取るソーラーパネルには、p型半導体とn型半導体があり、半導体内部の光電効果によって、電子と正孔が生成されます。
そこで発生した電荷が半導体内で分離し、移動することによってエネルギーとなり、電気を生み出しているのです。
発電した電気の流れ
太陽光発電により発電した電気は、主に次の用途で使用します。
- 自家消費
- 売電
- 蓄電
<発電した電気の流れ>
家庭用太陽光発電の場合、もっとも多く利用するのは自家消費です。エアコンや冷蔵庫、照明などの家電製品を動かす電力として利用できるため、電力会社から購入する電気の量を削減し、電気代を節約できるでしょう。
また、余った電力は電力会社に売電できるため、無駄が生じません。
パワーコンディショナーや蓄電池の役割
パワーコンディショナーは、発電した電気を直流(DC)から交流(AC)に変換する役割を持つ装置です。
太陽光発電によって生み出された電気は直流ですが、家庭やオフィスなどでは交流の電気を使用します。
そのため、パワーコンディショナーは太陽光発電に不可欠な装置です。
一方の蓄電池は、発電した電力を蓄える役割を果たす装置です。蓄電池を併用することにより、夜間や天候不良の日中といった太陽が出ていない時間帯でも、太陽光発電で生み出した電力を利用できます。
また、災害時など、停電時の非常用電源として使用することも可能です。
太陽光発電を支える機器
太陽光発電を支える機器は、全部で6つです。
- 太陽電池モジュール(ソーラーパネル)
- 接続箱
- 分電盤
- パワーコンディショナー
- 蓄電池
- モニター・電力量計
<太陽光発電を支える機器>
それぞれの特徴をご紹介します。
太陽電池モジュール(ソーラーパネル)
太陽電池モジュールとは、太陽電池セルと呼ばれる発電部分を集め、封止したパネルです。
太陽光発電を導入している家庭の屋根に載っている、魚の鱗のような物体といえばわかりやすいでしょう。
太陽電池モジュールを直列につなげたものを「ストリング」、並列につなげたものを「アレイ」と呼びます。太陽電池モジュールの種類は、主に以下の5つです。
- シリコン太陽電池
- CdTe太陽電池
- ペロブスカイト太陽電池
- CIS太陽電池
- 有機太陽電池
<太陽電池モジュールの種類>
2022年に導入された太陽電池のシェア率は、約97.5%がシリコン太陽電池、2.5%がCdTe太陽電池でした。
近年では、ペロブスカイト太陽電池も、新型の太陽電池として注目を集めています。
接続箱
接続箱とは、太陽電池モジュールの配線をひとつにまとめるために使う箱です。
太陽光発電の導入後は定期的な点検を行いますが、この際に使用するブレーカーや避雷針、電気の逆流を防ぐ逆流防止ダイオードといった装置も、接続箱に内蔵されています。
分電盤
分電盤とは、太陽光発電システムで発電した電気や、電力会社から供給される電気を、家庭内へ分配するために使う装置です。
また、余剰電力を売る際にも、分電盤を使用します。さらに、過電流や漏電といったトラブルを防ぐうえでも、重要な役割を担う装置です。
パワーコンディショナー
パワーコンディショナーは、直流から交流に変換する役割を持つ装置です。また、太陽電池モジュールによる発電能力を最大化する役割も担います。
電力会社から供給される配電線に連結する機能を持ち合わせており、電圧や周波数に合った電力を出力させられます。
蓄電池
蓄電池とは、太陽光発電装置で発電した電気を貯められる装置です。蓄電池があると、夜間や天候不良時など、太陽光発電ができない時間帯でも電力を自家消費できます。また、災害などによる停電時には、非常用電源として活用できます。
モニター・電力量計
モニターとは、太陽光発電システムの発電状況や、電力の消費状況をリアルタイムで表示する装置です。
売電量も確認できるため、エネルギー収支の確認や節電意識の向上にも役立ちます。
また、システム異常が発生した場合は、その内容がモニターに表示されることもあります。
電力量計とは、電力の流れを計測するメーターのことです。電力会社から購入した電力を計測する「買電メーター」と、余剰電力を売却した電力を計測する「売電メーター」があります。
また近年では、より詳細な電力使用状況を確認できる「スマートメーター」も普及しています。
太陽光発電の発電量と発電効率
太陽光発電の導入を検討している方は、実際にどのくらいの発電量が期待できるのかが、気になるのではないでしょうか。
ここでは、太陽光発電の発電量と発電効率について、3つのポイントから解説します。
- 1日・1年でどれくらい発電できる?
- 発電量に影響する要素
- 発電効率を上げるためのポイント
<太陽光発電の発電量と発電効率>
それぞれを具体的に見ていきましょう。
1日・1年でどれくらい発電できる?
太陽光発電の発電量は、後述するようにいくつかの要素に左右されますが、平均すると次のとおりです。
【太陽光発電の1日・1年の発電量(目安)】
| 項目 | 発電量 |
|---|---|
| 1日の発電量 | 3.4kWh前後 |
| 1年の発電量 | 1,000kWh前後 |
※システム容量1kWの場合
- 1kW×24時間×365日×14%=1,226kWh
<1年間あたりの発電量の計算式(システム容量1kWの場合)>
同じ要領で、1日あたりの発電量も計算してみましょう。
- 1kW×24時間×14%=3.4kWh
<1日あたりの発電量の計算式(システム容量1kWの場合)>
なお、環境省の発表によると、一般家庭における平均的な消費電力は、11.4kWhです。この消費電力をすべて太陽光発電で賄いたい場合は、システム容量4kWの太陽光発電システムを用意するとよいでしょう。この場合、1日あたり13.6kWhを発電できる計算です。
発電量に影響する要素
発電量に影響する要素は、全部で7つあります。
- 日射量
- 日陰
- パネルの設置角度
- 気温
- 風速
- 太陽電池モジュールの汚れ
- 機器の劣化
<太陽光発電の発電量に影響する要素>
特に大きく影響するのは、日射量です。季節や天候の影響を受けて、発電量が大きく変化します。
太陽電池モジュールが汚れていると、発電効率が下がるため、定期的にメンテナンスをすることも重要です。また、機器が劣化すると性能が低下し、発電量に影響する場合があります。
発電効率を上げるためのポイント
太陽光発電の発電効率を上げるポイントは、次のとおりです。
- 日照時間が長い場所に太陽電池モジュールを設置する
- 高効率な太陽電池モジュールを購入する
- 定期的にメンテナンスを行う
- 周辺機器を効率化する
<発電効率を上げるためのポイント>
先述したとおり、太陽光発電の発電量は、日射量によって大きく左右されます。そのため、日照時間が長く、日陰が少ない場所に、太陽電池モジュールを設置することが重要です。
メーカーのカタログなどを見ながら、変換効率の高い太陽電池モジュールを選ぶこともポイントといえます。
定期的なメンテナンスを行うことも大切です。太陽電池モジュールの表面に、落ち葉や鳥の糞といった汚れが付着すると、発電効率が下がります。
これらの汚れは、雨水や風で自然に落ちる場合もありますが、やわらかいブラシで軽くこするといったメンテナンスを欠かさぬようにするとよいでしょう。
太陽光発電のメリット・デメリット
【太陽光発電のメリット・デメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
余剰電力を売る際は、一定期間にわたり「FIT制度」を適用できます。国が定めた金額で、電力の買取が保証されるため、売電によって得られる収入の目途をつけやすいでしょう。
詳しくは太陽光発電のメリット・デメリットをわかりやすく解説!おすすめできるケースとは?でご紹介しています。関連記事もあわせて、参考にしてみてください。
太陽光発電の導入ステップ
太陽光発電の導入ステップは、次のとおりです。
- ステップ①情報収集を行う
- ステップ②現地調査と見積もりを依頼する
- ステップ③業者と契約し設計・申請手続きを行う
- ステップ④設置工事を行い試運転する
- ステップ⑤利用を開始する
<太陽光発電の導入ステップ>
順番にポイントをご紹介します。
ステップ①情報収集を行う
まずは、太陽光発電システムに関する基本的な情報を収集します。購入を希望する装置の種類や、工事を依頼する業者について下調べをしましょう。
ステップ②現地調査と見積もりを依頼する
専門業者に現地調査を依頼し、見積もりをとります。見積もりでは、機器の購入費や工事費といった費用相場に加えて、年間の発電量などのシミュレーション結果も確認できます。
ステップ③業者と契約し設計・申請手続きを行う
提示された見積もりに問題がなければ、業者と契約して設計・申請の手続きに進みましょう。
条件を満たす場合、国や自治体から補助金を受け取れる可能性があります。
ステップ④設置工事を行い試運転する
業者と工事日程の調整を行い、設置工事を行います。工事後は試運転し、システムが正常に稼働するかどうかを確認します。
ステップ⑤利用を開始する
試運転に問題がなければ、利用開始です。業者によるアフターフォローも受けながら、定期的にメンテナンスを行いましょう。
まとめ
太陽光発電は、光電効果と呼ばれる物理現象を利用して、発電する仕組みです。発電量の目安は、次のとおりです。
【太陽光発電の1日・1年の発電量(目安)】
| 項目 | 発電量 |
|---|---|
| 1日の発電量 | 3.4kWh前後 |
| 1年の発電量 | 1,000kWh前後 |
太陽光発電のメリットやデメリットも確認したうえで、導入を検討することをおすすめします。

エコモは各地を飛び回って、電力・エネルギーや地球環境についてお勉強中なんだモ!色んな人に電気/ガスのことをお伝えし、エネルギーをもっと身近に感じてもらいたモ!
宜しければSNSでのシェアをお願い致します!