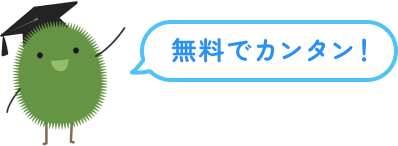PPAとは?電力の新しい調達方法と仕組みを環境省の方針とともに解説
太陽光発電に興味を持っている人の中には、デメリットが気になって導入に踏み切れない人も多いでしょう。
「初期費用が高い」「メンテナンスの手間がかかる」など、太陽光発電のデメリットを解消する電力契約モデルが「PPA」です。この記事では、PPAの仕組みやメリット・デメリットなどを解説します。
PPAとは?
PPA(Power Purchase Agreement)とは、太陽光発電システムの設備を初期費用0円で導入でき、メンテナンスも委託できるビジネスモデルです。
日本語に直訳すると「電力販売契約」となり、「第三者所有モデル」とも呼ばれています。まずはPPAの概要を整理しましょう。
- 太陽光発電の新しい電力契約モデル
- なぜ今「PPA」が注目されているのか
<PPAとは?>
一つずつ解説します。
太陽光発電の新しい電力契約モデル
PPAは、太陽光発電の新しい電力契約モデルです。PPAでは、まずPPA事業者と契約して、自宅の屋根などに太陽光発電システムを設置してもらいます。
契約期間中、利用者はPPA事業者に電気代を支払いますが、契約期間満了後は設備を譲り受けることが可能です。
PPAが誕生した背景には、再生可能エネルギーの普及が迫られている点が挙げられます。
しかし、高い初期費用や維持管理の手間は、一般家庭や中小企業の再エネ導入を妨げる一因になっていました。
PPAの登場により、これらの課題の解消に向かうことが期待されています。
なぜ今「PPA」が注目されているのか
今PPAが注目されている理由は、次のとおりです。
- 初期費用ゼロで太陽光発電を導入できるため
- 電気代が高騰しているため
- 維持管理の手間を省ける事業モデルであるため
- 卒FITに注目が集まっているため
<今PPAが注目されている理由>
電気代の高騰により、太陽光発電などの自家発電が注目されています。しかし、太陽光発電の導入には、高額な初期費用が発生することがデメリットです。
PPAは初期費用をゼロに抑えられるほか、メンテナンスもPPA事業者に任せられるため、太陽光発電導入へのハードルが低く、注目されています。
また、FIT制度(固定価格買取制度)から卒FITへと移行する家庭が増えたことも、PPAが注目されている理由のひとつです。
長期間の契約を結ぶPPAは、卒FIT後の価格変動リスクを緩和しやすいため、売電による収入を安定させやすくなります。
PPAモデル以外の導入方法との比較
PPAは、太陽光発電を導入する方法のひとつに過ぎません。PPA以外の導入方法について、PPAとの違いを比較しながら解説します。
- 自己所有型との違い
- リースとの違い
<PPAモデル以外の導入方法との比較>
それぞれを具体的に見ていきましょう。
自己所有型との違い
自己所有型とは、家庭や会社が太陽光発電システムを購入して、維持管理する方法です。PPAとの違いを比較してみましょう。
| PPA | 自己所有型 | |
|---|---|---|
| 所有者 | PPA事業者 | 各家庭や企業 |
| 初期費用 | かからない | かかる |
| 利用料 | かからない | かからない |
| メンテナンス | 不要 | 必要 |
| 自家消費分の電気代 | 有料 | 無料 |
| 売電収入 | なし | あり |
| 契約期間 | 10年~20年 | なし |
設備の購入から管理までを自分自身で行うため、初期費用や維持費がかかることが自己所有型の特徴です。
従来、太陽光発電といえば、自己所有型を指すケースが一般的でしたが、卒FIT後の売電収入を得にくいため、PPAが人気や注目度を高めています。
リースとの違い
リースとは、リース事業者から太陽光発電システムを借りて、運用する方法です。PPAとリースの違いを比較してみましょう。
| PPA | リース | |
|---|---|---|
| 所有者 | PPA事業者 | リース事業者 |
| 初期費用 | かからない | かからない |
| 利用料 | かからない | かかる |
| メンテナンス | 不要 | 不要 |
| 自家消費分の電気代 | 有料 | 無料 |
| 売電収入 | なし | あり |
| 契約期間 | 10年~20年 | 10年~15年 |
リースの場合、原則として、リース料にメンテナンス費用が含まれています。そのため、設備が故障したとしても、追加費用は請求されません。
リースはPPAとの共通点が多いものの、費用を支払って設備をレンタルすることが特徴です。
そのため、自家消費分の電気代は無料になり、売電収入も得られます。
PPA導入のメリット
PPA導入のメリットは、次のとおりです。
- 初期費用や維持費がかからない
- メンテナンスを第三者に任せられる
- 電気代を削減できる可能性が高い
- CO₂排出量の削減につながる
- 補助金・支援制度を活用できる
<PPA導入のメリット>
それぞれのポイントを解説します。
初期費用や維持費がかからない
PPAで特に大きなメリットとなるのが、初期費用や維持費がかからないことです。
これらの費用はすべてPPA事業者が負担するため、金銭的なゆとりがなくても、自宅に太陽光発電システムを導入できます。
太陽光発電システムの導入にかかる費用は、小規模なものでも100万円単位におよぶ可能性があるほど、高額です。
そのため、太陽光発電を導入したくても、導入できない人は多いでしょう。維持費も年間で数万円~数十万円が発生する場合がありますが、この費用を負担する必要もありません。
メンテナンスを第三者に任せられる
太陽光発電の設置後には定期的なメンテナンスが必須ですが、この作業をPPA事業者に任せられることもメリットです。
維持費を抑えられることに加えて、管理にかかる手間も削減できます。
例えば、効率よく発電するためには、太陽電池モジュール(ソーラーパネル)に付着した鳥の糞や砂埃などを定期的に除去しなければなりません。
メンテナンスを怠ると、故障や火災といったトラブルに発展する可能性もありますが、このようなリスクも背負わずに済みます。
電気代を削減できる可能性が高い
PPA事業者が生み出す電気には、一般的な電力会社から電気を購入する際にかかる「再エネ賦課金」がかかりません。
再エネ賦課金とは、再生可能エネルギーの普及を促進するために、国民が負担している費用です。再エネ賦課金は定期的に見直されており、現在の金額は次のとおりです。
【再エネ賦課金】
| 期間 | 賦課金単価 |
|---|---|
| 2025年4月まで | 3.49円/kWh |
| 2025年5月~2026年4月まで | 3.98円/kWh |
※税込み
1ヶ月の消費電力を300kWhと仮定した場合、2025年5月以降の再エネ賦課金は1,194円におよびます。この分を削減できるため、電気代が安くなる可能性が高いでしょう。
CO₂排出量の削減につながる
太陽光発電は、発電時にCO₂(二酸化炭素)を排出しない再生可能エネルギーです。
また、太陽光発電パネルの生産時も、一般的な発電システムと比較して、あまりCO₂を排出しません。地球環境の改善に貢献できることも、PPAを利用するメリットといえます。
補助金・支援制度を活用できる
PPAの導入時には、補助金や支援制度を活用できる可能性があることもメリットです。詳しくは「PPA導入に活用できる補助金・支援制度」で後述します。
PPA導入のデメリット
PPA導入のデメリットは、次のとおりです。
- 契約期間が長い
- 設置場所や所有権に制限がかかる
- 自己所有型よりも電気代削減率が低い
- 譲渡後はメンテナンス費用を負担する必要がある
<PPA導入のデメリット>
それぞれのポイントを解説します。
契約期間が長い
契約期間は利用するPPA業者によって異なりますが、10年~20年と長期間になりがちです。
契約途中で解約すると違約金が発生するため、建物の老朽化に伴うリフォームや、建て替えに制限がかかりやすい点に注意しましょう。
設置場所や所有権に制限がかかる
以下のような立地の場合、PPAを利用できない場合があります。
- 日照量が不十分な場合
- 積雪や塩害などへの対策が必要な場合
- スペースが不足している場合
- 設置容量が少なすぎる場合
<PPAを利用できない土地の例>
また、契約期間中に関して、太陽光発電設備の所有権はPPA事業者が持ちます。そのため、設備を勝手に処分できません。
自己所有型よりも電気代削減率が低い
自己所有型と比較して、電気代を削減しにくいこともデメリットです。契約期間中は、売電による利益も得られないため、節約できていることを実感しにくいでしょう。
譲渡後はメンテナンス費用を負担する必要がある
PPAの契約期間満了後に、太陽光発電設備を譲り受ける場合は、その後のメンテナンス費用をすべて自分で負担する必要があります。
定期点検費用やパネルの清掃費用、故障時の修理費用や交換費用、保険料などを負担する必要があるほか、撤去時には工事費用や廃棄費用も支払わなければなりません。
PPAモデルを導入する流れ
PPAモデルを導入する流れは、次のとおりです。
- STEP1:契約交渉を行う
- STEP2:許認可申請を行う
- STEP3:設備の設置工事を行う
- STEP4:運用開始
まずはPPA事業者を選定し、現地調査を依頼しましょう。ソーラーパネルの配置図や、パワーコンディショナーなどの設置場所、配線ルートを決定し、契約内容に合意できればPPA契約を締結できます。
建築基準法や電気事業法、消防法などに基づいて許認可申請を行います。これは、PPA事業者が代行するため、PPAの利用者には負担がかかりません。
屋根に架台をかけて、ソーラーパネルを設置します。パワーコンディショナーや接続箱などを事前の計画どおりに設置して、電気配線工事を行います。
設備の接続が終わり次第、電力の供給開始です。契約内容に基づいたPPA料金を支払いましょう。その後の定期点検やメンテナンスは、PPA事業者が適時実施します。
PPA導入に活用できる補助金・支援制度
PPA導入時には、国や自治体による補助金・支援制度を活用できます。一例として、環境省では「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(ストレージパリティ補助金)」を提供していました。
【二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の概要表】
| 補助対象となる設備 | 補助金 | 上限額 |
|---|---|---|
|
|
1.5億円(1需要地あたり) |
そのほかにも、各地自体が補助金や支援制度を提供している可能性があります。PPAモデルの導入時は、お住まいの市区町村HPなどを確認し、適用できる補助金や支援制度があるかを調べましょう。
まとめ
PPAとは、太陽光発電を導入する方法のひとつです。あらためてそのほかの導入方法と特徴を比較します。
| PPA | 自己所有型 | リース | |
|---|---|---|---|
| 所有者 | PPA事業者 | 各家庭や企業 | リース事業者 |
| 初期費用 | かからない | かかる | かからない |
| 利用料 | かからない | かからない | かかる |
| メンテナンス | 不要 | 必要 | 不要 |
| 自家消費分の電気代 | 有料 | 無料 | 無料 |
| 売電収入 | なし | あり | あり |
| 契約期間 | 10年~20年 | なし | 10年~15年 |
PPAのメリット・デメリットは、次のとおりです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
太陽光発電システムの導入を検討しているものの、初期費用の高さや維持管理の手間がネックで導入に踏み切れない場合は、PPAモデルの活用を検討すると良いでしょう。
また、補助金・支援制度を活用できる可能性もあるため、事前に市区町村HPなどを確認することをおすすめします。

エコモは各地を飛び回って、電力・エネルギーや地球環境についてお勉強中なんだモ!色んな人に電気/ガスのことをお伝えし、エネルギーをもっと身近に感じてもらいたモ!
宜しければSNSでのシェアをお願い致します!