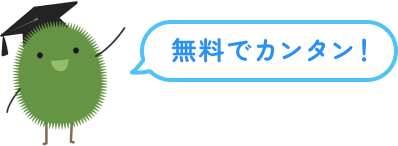蓄電池とは?基本的な仕組みや種類、太陽光発電と併用するメリットをわかりやすく解説
太陽光発電と同時に導入すると良い設備の一つが、蓄電池です。しかし、蓄電池がどのような仕組みなのか、導入するとどんなメリットを得られるのか、わからない方が多いかもしれません。
この記事では、蓄電池の仕組みについて、イラストを用いながらわかりやすく解説し、選び方や導入の流れもご紹介します。
蓄電池とは?
蓄電池とは、電気を貯めておき、必要なタイミングで使用できる装置です。身近な物に例えるならば、スマホのポータブルバッテリーをイメージすると、わかりやすいかもしれません。
まずは、蓄電池とはなにかを解説するために、蓄電池の概要をご紹介します。
- 充電して繰り返し使える電池のこと
- バッテリーとの違い
<蓄電池とは>
充電して繰り返し使える電池のこと
蓄電池とは、充電して繰り返し使える電池のことです。家庭用の蓄電池を導入すると、太陽光発電でつくった電気を貯めたり、電力会社から購入した電気を貯めたりできます。
これにより、電気を無駄なく使いやすくなることに加えて、停電時の非常用電源として利用できるなどのメリットを得られます。
バッテリーとの違い
蓄電池とバッテリーの違いは、充電して繰り返し利用できるかどうかです。
先述したように、蓄電池は充電して繰り返し使える電池を指しており、学術的には「二次電池」と呼ばれます。
一方のバッテリーは、電池全般を指す言葉です。「アルカリ電池」や「マンガン電池」のように、学術的に「一次電池」と呼ばれる、使い捨ての電池もバッテリーに含まれます。
そのため、蓄電池はバッテリーの一種と考えると良いでしょう。
【イラストつき】蓄電池の仕組みを簡単に解説!
蓄電池とは、先述したように、繰り返し利用できるバッテリーのことです。そこで気になるのは、どのような構造や仕組みで、充電・放電を繰り返しているのかという点でしょう。
ここでは、蓄電池の仕組みについて、イラストつきでわかりやすく解説します。
- 蓄電池の構造
- 放電の仕組み
- 充電の仕組み
<蓄電池の仕組みとは>
蓄電池の構造
蓄電池の構造は、以下のイラストのとおりです。
<イラストの挿入をお願いいたします>
一例として、リチウムイオン電池の場合、正極(プラス極)と負極(マイナス極)、セパレータ、そして電解液で構成されています。
正極と負極にはそれぞれ異なる物質が使われており、いずれも電解液に浸かった状態です。
また、これをセパレータが分け、正極と負極が触れてショートするのを防いでいます。
放電の仕組み
放電の仕組みをイラストで見てみましょう。

負極の勝つ物質が電子を放出し、それと同時にイオンが電解液に溶け出す「酸化反応」が発生します。
このとき、放出された電子は、電化製品などを通って正極へと向かいます。この電子の流れによって発生するのが、電気です。この流れで電気を使えるようになることを、放電といいます。
充電の仕組み
充電の仕組みをイラストで見てみましょう。
電流を流して負極に電子を取り込ませると、正極側にあるリチウムイオンが負極に移動して充電できます。
つまり、放電とは反対方面に電流を流すことにより、負極にリチウムイオンをためられるのです。
負極にリチウムイオンがたまると、再び放電できるようになり、放電と充電を繰り返せます。
蓄電池の主な種類
蓄電池の種類は、イラストで解説したリチウムイオン電池だけではありません。そのほかの主な種類と特徴を見てみましょう。
- 鉛蓄電池
- ニッケル水素電池
- リチウムイオン電池
- NAS電池・レドックスフロー電池
<蓄電池の主な種類>
鉛蓄電池
鉛蓄電池とは、電極に鉛を採用している蓄電池です。いくつかある蓄電池の種類の中でも、特に放電性能が安定しており、自動車のバッテリーや非常用電源として採用されています。
鉛蓄電池は、最も歴史が深い蓄電池の種類であり、リサイクル環境も整っています。原料として使われる鉛は安価なため、導入コストを抑えやすいことが鉛蓄電池のメリットです。
ただし、原料の鉛が重いため、蓄電池本体が重くなることは、デメリットと考えなければなりません。
ニッケル水素電池
ニッケル水素電池とは、電極にニッケル酸化化合物と水素化合物を採用している蓄電池です。
過充電や過放電への耐性が強く、ハイブリッドカーのバッテリーや乾電池などに多く採用されています。
ニッケル水素電池の歴史も深く、後述するリチウムイオン電池が主流になる前から普及しています。発火や爆発のリスクが低く、安全性が高いこともメリットです。
ただし、自然放電が多いことはデメリットであり、こまめに充電しなければ、電池切れを起こしてしまいます。
リチウムイオン電池
リチウムイオン電池とは、電極の間をリチウムイオンが移動することにより、充電と放電を行える蓄電池です。
住宅用蓄電池のほか、スマートフォンやタブレット、ノートパソコン、電気自動車のバッテリーなど、幅広い用途で使われています。
リチウムイオン電池のメリットは、エネルギー密度が高いことです。減量が軽いため、小型軽量かつ大容量の蓄電池を製造できます。
ただし、鉛蓄電池やニッケル水素電池と比較してコストが高いことや、熱暴走による発火・爆発のリスクがあることはデメリットです。
NAS電池・レドックスフロー電池
NAS電池(ナトリウム硫黄電池)とは、ナトリウムと硫黄を原材料とする蓄電池です。容量が大きいことが特徴で、商業施設や工場の蓄電池として採用されています。
ただし、高温で作動するため、電池を常に温める必要があることはデメリットです。
レドックスフロー電池(RF電池)とは、電極ではなく、電解液の酸化還元反応を利用して、充電と放電を繰り返す蓄電池です。
不燃性のため安全性が高く、半永久的に利用できるとされています。ただし、エネルギー密度が低いため、コンパクトには設計できません。
太陽光発電と蓄電池を併用するメリット
太陽光発電と蓄電池を併用するメリットは、次の3つです。
- 電気代の削減につながる
- 非常用電源として使える
- 余剰電力を買い取ってもらえる
<太陽光発電と蓄電池を併用するメリット>
それぞれのポイントを解説します。
電気代の削減につながる
太陽光発電と蓄電池を併用すると、住宅の電気代を削減できます。
太陽光発電は、日差しが出ている日中にしか行えません。しかし、日中に発電した電気を蓄電池に貯めておくことにより、夜間などの太陽光発電ができない時間帯も、電力を自家消費できます。
電気を電力会社から購入する必要がなくなるため、電気代を削減できるのです。
また、時間帯ごとに、従量料金が異なる電力プランに加入している場合は、電気代が安い時間帯に購入した電力を蓄電池に貯められます。
電気代が高い時間帯は、電気代が安い時間帯に購入した蓄電池の電力を使えるため、これも電気代の削減につながります。
非常用電源として使える
非常用電源として使えることも、蓄電池のメリットです。
災害時などに電力の供給がストップすると、家中の電気を使えなくなることは、太陽光発電の欠点といわざるを得ません。
しかし、あらかじめ蓄電池に電気を貯めておくと、緊急時の非常用電源として利用できます。地震や水害といったトラブルに備えたい方も、蓄電池を導入すると良いでしょう。
余剰電力を買い取ってもらえる
太陽光発電により発生した余剰電力は、電力会社に買い取ってもらえます。蓄電池を活用すると、売電量を増やせるため、売電による収入を増やしやすくなることがメリットです。
FIT制度(固定価格買取制度)の期間中は、国が定めた金額で売電できることが保証されています。
FIT終了後(卒FIT後)は、FIT期間中と比較して電力の買取価格が下がりますが、売電を続けることは可能です。
太陽光発電と蓄電池を併用するデメリット
太陽光発電と蓄電池を併用するデメリットは、次の2つです。
- 初期費用が高い
- 設置スペースに制約がかかる
<太陽光発電と蓄電池を併用するデメリット>
それぞれのポイントを解説します。
初期費用が高い
太陽光発電と蓄電池を併用する場合、導入時の初期費用が高いことはデメリットです。設備の購入費と工事費を合わせると、100万円単位の費用が発生する場合もあるでしょう。
また、蓄電池の点検や寿命管理、修理といったメンテナンス費用もかかります。これらの費用は、購入する蓄電池の種類によって異なるため、あらかじめ費用の目安を調べておきましょう。
ただし「住宅用蓄電池の導入に活用できる補助金制度について」でご紹介するように、蓄電池の購入時には、国や自治体の補助金を活用できる場合があります。
設置スペースに制約がかかる
蓄電池を設置するスペースや条件に、制約がかかることもデメリットです。
蓄電池を使うためには、一定のスペースが必要になるため、敷地の広さや形状によっては、蓄電池を設置できない可能性があります。
また、適切な温度に管理する必要があるほか、通気性の高い場所に設置する必要もあり、スペースがあったとしても設置工事が不可能な場合もあります。
住宅用蓄電池の選び方
住宅用蓄電池の選び方について、3つのポイントから解説します。
- 容量を選ぶ
- 機能を選ぶ
- 設置環境を選ぶ
<住宅用蓄電池の選び方>
それぞれを具体的に見ていきましょう。
容量を選ぶ
まずは、蓄電池の容量を決めましょう。普段の電力使用量やピーク時の需要、非常用電源として利用したいかどうかなどを加味しながら、必要な電力量を検討します。ポイントは、一度に使える電気の出力量も併せて、確認することです。
機能を選ぶ
蓄電池の機能はさまざまです。ケースごとに見た最適な機能をご紹介します。
- 停電時も家電を使いたいなら…全負荷対応ハイブリッド型
- 電気代を削減したいなら…ハイブリッド型
- すでに太陽光発電を導入しているなら…単機能型
<ケースごとに見た蓄電池の最適な機能>
設置環境を選ぶ
設置環境の確認も必要です。それぞれの特徴を見てみましょう。
- 屋内設置…災害時の浸水リスクを抑えられる
- 屋外設置…屋内に設置スペースを確保する必要がない
<設置環境ごとの特徴>
住宅用蓄電池を導入する流れ
住宅用蓄電池を導入する流れは、次のとおりです。
- STEP1:見積もりを依頼する
- STEP2:現地調査を行う
- STEP3:各種申請を行う
- STEP4:設置工事を行い利用開始
まずは、蓄電池を販売する取扱店やハウスメーカーに見積もりを依頼しましょう。
業者が決まり次第、現地調査を受けて、設置スペースや配線の接続方法などを確認します。
国や電力会社に設置の申請を行います。補助金の申請も同時に行いましょう。
業者による設置工事が行われ、試運転の結果に問題がなければ利用開始です。
住宅用蓄電池の導入に活用できる補助金制度について
一定の条件を満たす場合、住宅用蓄電池の導入時に補助金を受け取れます。適用できる可能性のある補助金は、次のとおりです。
- ZEH支援事業
- DR家庭用蓄電池事業
- 子育てグリーン住宅支援事業
<適用できる可能性のある補助金>
それぞれ適用条件が異なるため、事前に詳細を確認しましょう。
まとめ
蓄電池とは、繰り返し使えるバッテリーのことです。蓄電池には「鉛蓄電池」や「ニッケル水素電池」などいくつかの種類があり、それぞれ特徴が異なります。
住宅に蓄電池を導入するメリット・デメリットは、次のとおりです。
【蓄電池を太陽光発電と併用するメリット・デメリット】
| メリット | デメリット |
|---|---|
|
|
蓄電池は、太陽光発電との相性が良い設備です。太陽光発電の導入を検討している場合は、蓄電池を併用することをおすすめします。

エコモは各地を飛び回って、電力・エネルギーや地球環境についてお勉強中なんだモ!色んな人に電気/ガスのことをお伝えし、エネルギーをもっと身近に感じてもらいたモ!
宜しければSNSでのシェアをお願い致します!