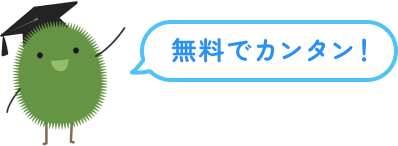オール電化に必要なアンペア数とは?目安・確認方法・契約のポイントを解説
オール電化の導入を検討している方の中には「契約アンペア数はどれくらいがいいんだろう」と気になっている方も多いでしょう。
アンペア数が適切でない場合、無駄な出費が発生したり、ブレーカーが落ちやすくなったりするため、注意が必要です。
この記事では、オール電化に必要なアンペア数の目安や、計算の仕方について解説します。アンペア数の確認方法や変更手続きについても触れているので、ぜひ参考にしてみてください。
アンペアとは?
私たちの生活に欠かせない電気は、電気の契約において「アンペア(A)」という単位が存在します。まずは、オール電化で重要となるアンペアについて解説します。
アンペアの基本的な意味
アンペアとは、導線のある断面を1秒間に通過する電子の個数を表す単位です。簡単に説明すると、一度に流れる電気の量を表す単位であり、電流の大きさと言い換えられます。
家庭におけるアンペアの役割と重要性
家庭におけるアンペアには、一度に使える電気量の上限値としての役割があります。日常生活で電気を使用する機会は多いですが、契約アンペア数以上の電気を使うと、ブレーカーが落ちる仕組みになっています。つまり、アンペア数は、家庭において最大限に使える電気量を示した数値だといえるのです。
また、電気の契約は、アンペア数が高くなるほど基本料金も高くなります。アンペア数を高くしすぎると、無駄な出費が増えてしまうため、慎重に検討しましょう。
オール電化に必要なアンペア数の目安
オール電化に必要なアンペア数は、60A以上が目安です。しかし、必要なアンペア数は、家族の人数や使用する家電によって異なります。
ここでは、3つのケースに分けて、オール電化に必要なアンペア数の目安をご紹介します。
一人暮らしの場合
一人暮らしの場合、40Aほどで事足りるケースが多いです。電気の使い方によっては、20〜30Aで対応できることもあるでしょう。
しかしながら、一人暮らしでもテレビやエアコン、電子レンジなど、複数の電化製品を同時に使用する機会は多いため、基本的に40Aの契約を検討したほうが良いでしょう。
二人暮らし・家族世帯の場合
二人暮らしや家族世帯に関しては、50〜60Aが一つの目安とされています。二人暮らしの場合、同時に使用する電気量が一人暮らしと変わらないこともあり、40Aほどで足りるという方もいます。
一方で、家族世帯は同時に使用する電気量が必然的に増えるため、少なくとも50〜60Aで契約しておくと安心です。
同居している家族の人数が多い場合や、同じタイミングで複数の家電を使用する場合は、60A以上で契約することも視野に入れておきましょう。
エコキュートなど高消費電力家電を使う場合
消費電力が高い家電を使うとなれば、それ相応の電気量が必要になります。例えば、エコキュートのアンペア数は15〜20A、IHクッキングヒーターのアンペア数は15〜30Aが目安です。
これらの高消費電力家電を同時に使うとなると、一人暮らしや二人暮らしであっても、60A以上が必要になるケースもあるでしょう。よって、アンペア数は、家電の消費電力も考慮して決定することが重要といえます。
アンペア数を確認する方法
そもそも、現在契約しているアンペア数が分からないという方も多いでしょう。ここからは、アンペア数を確認する方法について解説します。
分電盤で確認する方法
現在契約しているアンペア数は、分電盤の中にあるブレーカーに書かれた数字や色で判断できます。例えば、ブレーカーに「60A」と書かれている場合、そのお住まいの契約アンペア数は「60A」です。
また、電力会社の中には、アンペア数を色分けしているところもあります。それぞれの色が示すアンペア数については、各社のホームページにてご確認ください。
なお、アンペア制が導入されていない地域では、一般的な住宅は50A、オール電化住宅は60Aや100Aで設定されていることが多いです。
電力会社の請求書や検針票で確認する方法
電力会社から送付される請求書や検針票にも、契約中のアンペア数が載っています。近年はペーパーレス化で紙の請求書・検針票がなくなってきているものの、電力会社の会員ページにログインすれば、契約しているアンペア数を確認することが可能です。
オール電化で必要なアンペア数を計算する方法
ここまで解説してきたとおり、オール電化住宅で快適に過ごすためには、適切なアンペア数を選ぶことが重要です。
では、必要なアンペア数はどのようにして求めれば良いのでしょうか。以下でご紹介する計算方法を参考に、ご自身の生活環境に合ったアンペア数をチェックしてみましょう。
家電ごとの消費電力とアンペアの計算方法
オール電化で必要なアンペア数は、同時に使用する家電のアンペア数を合計すれば、おおよその値を算出できます。
加えて、各家電のアンペア数は「消費電力(W)÷ 電圧(V)」の計算式で求めることが可能です。
例えば、消費電力が1300Wの電子レンジを100Vの電源で使用する場合、アンペア数は13A(1300W÷100V=13A)となります。代表的な家電の消費電力の目安は、以下のとおりです。
【代表的な家電の消費電力の目安】
| 家電 | 消費電力の目安 |
|---|---|
| IHクッキングヒーター | 3000W |
| 電子レンジ | 1300W |
| アイロン | 1300W |
| ドライヤー | 1000W |
| 洗濯機 | 500W |
| エアコン(6畳) | 450W |
| 冷蔵庫 | 300W |
| 液晶テレビ(32インチ) | 50W |
| ノートパソコン | 30W |
なお、各家電の消費電力は、メーカーやサイズ、使い方などによって異なります。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。
家族の人数に応じた必要アンペアの算出
家電のアンペア数を合算するほか、家族の人数に応じて必要なアンペア数も算出できます。一般家庭におけるアンペア数の目安は、以下のとおりです。
- 1〜2人の場合:30〜50A
- 2〜3人の場合:40〜60A
- 3〜4人の場合:60〜80A
- 4〜5人の場合:60〜100A
<一般家庭におけるアンペア数の目安>
ここで注意したいのが、上記のアンペア数はあくまで目安であることです。先ほどお伝えしたとおり、オール電化で必要なアンペア数は、電気の使い方や使用する家電によっても変わってきます。
例えば、消費電力が高い家電をよく使う場合は、表中の数値よりも高いアンペア数の契約を検討したほうが良いでしょう。
アンペア数に余裕を持たせておかないと、ブレーカーが頻繁に落ちてしまい、快適性が損なわれる恐れがあります。
必ずしも目安のアンペア数が最適とは限らないため、それぞれのライフスタイルや家電の消費電力などを踏まえて、契約するアンペア数を決定しましょう。
アンペア数を変更する手続きと注意点
契約アンペア数は、必要に応じて変更することが可能です。ここでは、アンペア数の変更方法と注意すべきことをご説明します。
アンペア数変更の具体的な手順
アンペア数の変更方法は、契約している電力会社に連絡するだけと簡単です。電話でアンペア数の変更希望の旨を伝える、もしくはインターネットから契約内容の変更を申し込みましょう。申し込みが完了すると、後日電力会社の職員がブレーカーの撤去・設置を行ってくれます。
工事や費用の目安
前述のとおり、アンペア数の変更手続きを行うと、後日ブレーカーの取り替え工事をしてくれます。一般的に、工事費用は無料ですが、特殊な作業を必要とする場合は有料になることもあるでしょう。
アンペア数を変更するときは、あらかじめ工事にかかる費用や時間について確認しておくと、より安心です。
アンペア数変更時に知っておくべき注意点
アンペアを変更する際は、いくつか注意すべきポイントがあります。ここからは、事前に知っておきたい注意点を3つご紹介します。
停電期間の発生
ブレーカーの撤去・設置を行っている間は、電気が使えません。1時間ほどの停電が発生するため、仕事や家事に影響が出ないよう、準備しておく必要があります。
契約は原則1年に1回変更可能
契約アンペア数の変更は、原則として1年に1回しか行えません。そのため、1年単位での電気使用を想定し、適切なアンペア数を見極めることが求められます。
アンペア数の下げすぎにはリスクがある
アンペア数の下げすぎは、ブレーカーが落ちやすくなる原因となります。ブレーカーが頻繁に落ちるようになれば、快適性が損なわれるだけでなく、家電の故障にもつながりかねません。
このような事態を避けるためには、無理にアンペア数を下げず、少し余裕を持たせておくことが重要です。
アンペア数が電気料金に与える影響
アンペア数は、電気料金に関わる重要な要素の一つです。具体的にどのような影響があるのか、詳しく見ていきましょう。
オール電化住宅における電気料金の仕組み
最もポピュラーな電気料金プランである「従量電灯」は、契約アンペア数に応じて、基本料金が高くなる仕組みになっています。加えて、電気使用量に応じて、電気料金が発生するのも特徴です。
オール電化住宅ではガスを使わず、すべての熱源を電気で賄うため、一般的な住宅よりも電気使用量が増えます。
ガスの契約が不要になる分、光熱費を安く抑えられる可能性がありますが、電気代の負担が増えることは頭に入れておかなければなりません。
なお、オール電化住宅での電気代平均額は、 年間で190,000円程度とされています。電気料金は、契約プランなどによって大きく変わるため、あくまで目安としてご参考ください。
アンペア制を採用していない地域の場合
関西電力をはじめ、中国電力・四国電力・沖縄電力では、アンペア制を採用していません。これらの管轄エリアに住んでおり、大手電力会社と契約している場合は、電気使用量に応じた最低料金を支払うのが一般的です。このような方式を最低料金制といいます。
オール電化とアンペアに関するよくある質問
ここからは、オール電化とアンペアに関するよくある質問にお答えしていきます。オール電化の導入やアンペア数の変更を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
【Q1】オール電化で最適なアンペア数はどれくらいですか?
オール電化のアンペア数は「60A」以上が一般的です。60Aで契約すれば、ブレーカーが落ちにくくなるため、快適な暮らしを実現しやすいでしょう。
しかしながら、オール電化で必要なアンペア数は、家族の人数や使用する家電によって異なります。そのほか、ライフスタイルによっても変わってくるため、それぞれの家庭に合ったアンペア数を選ぶことが大切です。
【Q2】60A以上の契約をするにはどうすればいいですか?
60A以上の契約を希望される場合は、現在契約している電力会社に相談しましょう。必要に応じて60A以上の契約をすることは可能ですが、その場合は幹線の張り替え工事や、分電盤の取り替え工事などを行わなくてはなりません。電力会社の指示に従い、必要な手続きを済ませましょう。
【Q3】エコキュート使用時に注意すべき点は?
エコキュートは消費電力が高く、使用時は15〜20A程度の電力を消費します。複数の家電や高消費電力家電と同時に使用すると、ブレーカーが落ちる可能性があるので注意が必要です。エコキュートを導入している住宅においては、リスクヘッジとして60A以上で契約することをおすすめします。
オール電化アンペアまとめ
自宅で一度に使用できる電気量は、契約するアンペア数によって決まります。契約アンペア数以上の電気を使用すると、ブレーカーが落ちるように設定されているため、どれくらいのアンペア数が必要なのかを事前に把握しておくことが重要です。
また、アンペア数が高いと無駄な電気代がかかってしまい、逆に低いとブレーカーが落ちやすくなってしまいます。
オール電化住宅では60Aでの契約が多く見られますが、これはあくまで一つの目安にすぎないため、ライフスタイルに合わせた契約で快適な暮らしを実現しましょう。

エコモは各地を飛び回って、電力・エネルギーや地球環境についてお勉強中なんだモ!色んな人に電気/ガスのことをお伝えし、エネルギーをもっと身近に感じてもらいたモ!
宜しければSNSでのシェアをお願い致します!