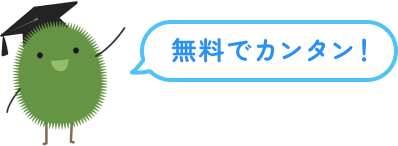オール電化の未来はどうなる?電気代高騰と節約対策を徹底解説
近年の電気代高騰により、エネルギーのすべてを電力でまかなうオール電化の未来に、不安を抱えている方は多いかもしれません。そこで今回は、オール電化の電気代が今後どうなるのか、ガス併用との比較も交えながら解説します。
オール電化の今後はどうなる?市場動向と背景

オール電化の導入を検討している方にとって、近年の電気代高騰は気になるトピックです。オール電化の現状と今後について、3つのポイントから解説します。
- オール電化の普及状況と現状
- オール電化を取り巻く環境変化(電力政策・エネルギー事情)
- 脱炭素社会に向けた電化住宅の役割
<オール電化の今後はどうなる?市場動向と背景>
それぞれを具体的に見ていきましょう。
オール電化の普及状況と現状
オール電化住宅は2000年ごろから普及しはじめ、全体では10%、新築住宅に限定すると約30%がオール電化にシフトしています。
2016年4月には電力小売業が自由化され、より低価格で電力を使用できるようになったことも、オール電化の普及が進んだ理由のひとつです。
しかし、ここ数年は、ウクライナにおける戦争などの影響に伴う電気代の高騰により、オール電化の需要にも影響が生じています。
リモートワークの増加によって、家庭で消費する電力量が増えたこともあり、オール電化市場の拡大が鈍化しているのが現状です。
オール電化を取り巻く環境変化(電力政策・エネルギー事情)
オール電化の電力政策としては、新築住宅のオール電化を奨励する政策や、ZEH住宅の促進などがあります。脱炭素化の流れが世界的な主流となっており、現在は再生可能エネルギーの普及が加速中です。
オール電化住宅は太陽光発電を取り入れているため、地球温暖化の解決策としても注目されています。
脱炭素社会に向けた電化住宅の役割
太陽光発電により、家庭内の電力をまかなうオール電化住宅は、脱炭素社会に向けて大きな役割を果たすでしょう。
オール電化住宅はCO2を排出するガスを使わないため、地球温暖化の抑制に貢献できます。また、太陽光発電で作った電力を使用することにより、さらにCO2の排出量を削減できます。
オール電化のメリット・デメリット
オール電化を導入するべきか悩んでいる方にとって、気になるのは導入によるメリットとデメリットでしょう。ここでは、オール電化のメリットとデメリットについて、簡単に解説します。
オール電化のメリット
オール電化のメリットは、次の5つです。
- 光熱費を一本化できる
- 火災リスクを低減できる
- IHクッキングヒーターで掃除が楽
- エコキュートを災害時に利用できる
- 太陽光発電・蓄電池との相性が良い
<オール電化のメリット>
オール電化では、電気とガスの光熱費を一本化できます。支払いの管理が楽になることに加えて、基本料金の支払いも電気に統一できるため、光熱費を削減しやすいでしょう。
ガスコンロからIHクッキングヒーターに交換することにより、火災リスクも低減できます。また、IHクッキングヒーターは、ガスコンロと比較して構造がシンプルです。表面を拭くだけで掃除が完了するため、お手入れの手間もかかりません。
エコキュートに水がたまっている場合は、災害時にも飲用以外の生活用水として利用できることもメリットです。
さらに、太陽光発電や蓄電池との相性も良く、併用すると光熱費を削減しやすいでしょう。
オール電化のデメリット
オール電化のデメリットは、次の4点です
- 昼間の電気料金が高い
- IH対応の調理器具が必要になる
- 給湯の水圧が弱くなる可能性がある
- 設備導入コストが高い
<オール電化のデメリット>
オール電化向けの料金プランは夜間が安く、昼間は高いことが特徴です。日中の在宅時間が長い方の場合、電気料金が高くなる可能性があるでしょう。
原則として「IH対応」の調理器具しか使えないため、状況に応じて調理器具の買い直しが必要になることもデメリットです。
また、給湯の水圧がガス給湯器と比べて弱くなる可能性もあり、水圧を重視する場合は、高水圧タイプのエコキュートを購入しなければなりません。
さらに、設備導入コストが高いことも、オール電化の欠点です。ただし、ガス併用と比べて光熱費のランニングコストを抑えられるため、長い目で見れば得になる可能性があります。
オール電化の電気代は今後どうなる?値上げの背景
電気代の急騰が続いているため、オール電化の電気代が今後どうなるか気になる方が多いでしょう。オール電化の展望について、値上げの背景も交えながら解説します。
- 電気代が高騰している理由
- 今後の見通しとオール電化住宅への影響
<オール電化の電気代は今後どうなる?値上げの背景>
それぞれを具体的に見ていきましょう。
電気代が高騰している理由
電気代が高騰している理由としては、次の3点が挙げられます。
- 燃料費調整額の上昇
- 再エネ賦課金の増加
- 電力会社の値上げ
<電気代が高騰している理由>
燃料調整額とは、燃料費の変動を反映させた調整額です。近年は、ウクライナ戦争や原子力発電所の停止により燃料費調整額が上昇しており、これが電気代の高騰の一因になっています。
省エネ賦課金は、再生可能エネルギーの普及を目的として電気料金に上乗せされるもので、こちらも上昇傾向が見られます。
これらの事情により、電力会社が値上げを行った結果、以前と変わらない電力消費量にも関わらず、電気代が高くなるケースが増えているのです。
今後の見通しとオール電化住宅への影響
2025年1月から政府の補助が再開することになり、直近では電気料金が値下がりする見通しとなっています。
ただし、2050年までの燃料価格の見通しについて、EIA(米国エネルギー省エネルギー情報局)は、天然ガスと石炭の両方の値上がりが続くと予測しています。
天然ガスと石炭の値上がりは、日本の電気料金に直結するため、政府による補助がストップした場合は、電気代の値上がりを覚悟しなければなりません。
オール電化住宅において電気代を削減するためには、エネルギーの使い方や設備、電気料金の見直しといった対策が必要です。
オール電化の電気代を抑える方法

オール電化の電気代を抑える方法としては、次の3つが有効です。
- エネルギーの使い方を見直す
- 設備の見直し・導入を行う
- 電力プランを最適化する
<オール電化の電気代を抑える方法>
それぞれのポイントを解説します。
エネルギーの使い方を見直す
エネルギーの使い方を見直すことが、オール電化の電気代を抑えるための第一歩です。オール電化向けの料金プランは、夜間に安く、昼間は高く設定されています。日中に電力消費量が多い場合は、日中の節電を心がけると良いでしょう。
例えば、エコキュートの場合、日中に沸き増しするなどの使い方をすると、電気料金が大幅に上がる可能性があります。
日中にお湯切れを起こさないように十分な湯量を蓄えたり、夜間のみ稼働するように設定したりするなどの対策をすると効果的です。
消費電力が大きいエアコンの設定温度を変えることもおすすめします。設定温度を1度上げ下げするだけでも、電気代を大幅に削減できるでしょう。洗濯機のすすぎを2回から1回に減らすなどの対策も、電気代を抑えるためのポイントになります。
設備の見直し・導入を行う
オール電化との相性が良い設備を導入したり、新しい設備に買い直したりする対策も有効です。家電の省エネ性能は高まり続けているため、新製品に買い替えると節電効果を得やすくなります。
家電の使用状況や消費電力を可視化できる「スマート家電」の導入もおすすめです。
予算を用意できる場合は、太陽光パネルや蓄電池の導入も検討すると良いでしょう。太陽光パネルで自家発電した電力を用いると、電気代を削減しやすくなることに加えて、余剰電力は売電することによって現金化できます。
蓄電池を導入すると、太陽光パネルで発電した電力や、夜間の電気代が安い時間帯に購入した電力をためて、そのほかの時間帯に使用できます。
太陽光発電や蓄電池の導入時には、国や自治体からの補助金が支給される場合があり、お得に導入できる可能性もあるでしょう。
電力プランを最適化する
電力プランを最適化することも重要です。オール電化住宅に移行した後は、契約する電気料金プランをオール電化向けのプランに変更しましょう。
夜間の料金が安いオール電化向けのプランを契約すると、電気代が安い時間帯に沸かしたお湯を電気代が高い時間帯に使えるため、節約できます。
電力自由化以降は、東京電力や関西電力といった大手電力会社だけではなく、いわゆる新電力の会社とも自由に契約できるようになりました。
会社によって料金プランの特徴が異なるため、定期的に料金プランを見直して、最適な電力会社や料金プランに乗り換えることが重要です。
オール電化とガス併用の比較:どちらがお得?
現在は電気とガスを併用している方の場合、現状のまま維持するのとオール電化に移行するのとでは、どちらがお得になるのか気になるでしょう。
そこで、光熱費の比較をしたうえで、オール電化とガス併用それぞれが向いている家庭の特徴をご紹介します。
- 光熱費の比較
- オール電化が向いている家庭
- ガス併用が向いている家庭
<オール電化とガス併用の比較:どちらがお得?>
それぞれのポイントを詳しく見てみましょう。
光熱費の比較
関西電力が発表したデータによると、オール電化住宅の光熱費平均額は、家族構成ごとに次のとおりでした。
【オール電化住宅の光熱費平均額】
| 世帯人数 | 1人暮らし | 2人暮らし | 3人家族 | 4人家族 |
|---|---|---|---|---|
| 一戸建て | 15,311円 | 16,533円 | 17,617円 | 19,832円 |
【オール電化住宅とガス併用住宅の比較】
| オール電化住宅 | ガス併用住宅 | 収支 | |
|---|---|---|---|
| 1人暮らし | 10,777円 | 9,134円 | +1,643円 |
| 2人暮らし | 13,406円 | 14,824円 | -1,418円 |
| 3人家族 | 14,835円 | 16,574円 | -1,739円 |
| 4人家族 | 16,533円 | 17,617円 | -1,084円 |
電力消費量が少ない1人暮らしは、ガス併用住宅のほうが割安ですが、2人暮らし以上の家庭ではオール電化住宅のほうがお得です。
3人家族の場合、1ヶ月あたり1,739円もお得になるため、単純計算すると年間で20,868円も光熱費を節約できます。
20年間に換算すると、約40万円の節約につながり、オール電化導入にかかる初期費用の大半を相殺できる可能性があるでしょう。
オール電化が向いている家庭
オール電化が向いている家庭は、次のとおりです。
- 災害時の備えを重視する家庭
- 太陽光発電・蓄電池を活用できる家庭
- 調理時の火を使わない安全性を求める家庭
<オール電化が向いている家庭>
火災のリスクを抑えたい家庭や、災害時に復旧しやすい体制を整えたい家庭にも、オール電化がおすすめです。
また、太陽光発電や蓄電池を活用できる場合は、節電効果を高めやすいため、オール電化の導入がおすすめです。
ガス併用が向いている家庭
ガス併用が向いている家庭は、次のとおりです。
- 給湯の水圧やガス火の料理を重視する家庭
- 寒冷地で暖房のコストを抑えたい家庭
- 初期導入コストを抑えたい家庭
<ガス併用が向いている家庭>
上記に該当する場合は、オール電化を導入するべきか慎重に検討しましょう。
まとめ
今後の脱炭素社会に向けて、オール電化住宅は大きな役割を果たします。ガス併用と比較すると、2人暮らし以上の家庭では電気代がお得になりやすく、今後も上昇する見込みの電気代を削減するうえでもオール電化が役立つでしょう。また、災害時の備えを重視する家庭などにも、オール電化をおすすめできます。

エコモは各地を飛び回って、電力・エネルギーや地球環境についてお勉強中なんだモ!色んな人に電気/ガスのことをお伝えし、エネルギーをもっと身近に感じてもらいたモ!
宜しければSNSでのシェアをお願い致します!