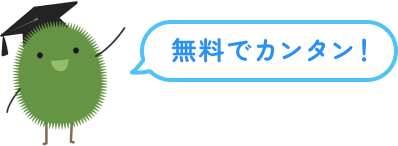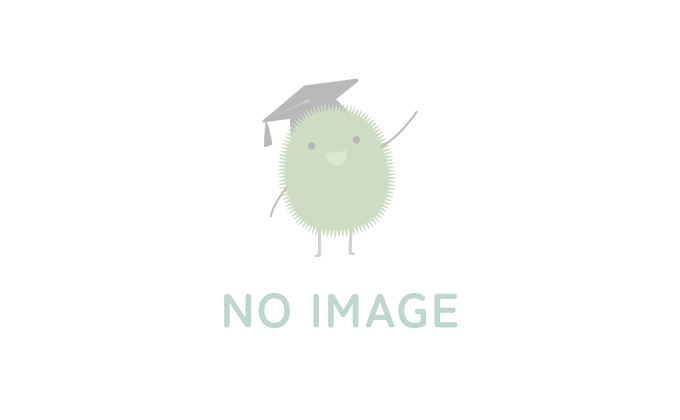【徹底解説】クリニックの電気代の内訳と削減ポイント|高騰対策で経営を守る
毎日のように多くの患者さんを迎えるクリニックでは、電気代が多くかかりがちです。
現在、電気料金は上昇傾向にあり、クリニックにおいても節電対策が求められています。
本記事では、クリニックの電気代が高くなる理由や主にどの部分で電力を消費しているのか、また電気代を削減するために取れる具体的な対策についてご紹介します。
クリニックの電気代削減について、関心のある方はぜひ最後までご覧ください。
クリニックの電気代はなぜ高くなりがちなのか?
クリニックの電気代は、一般家庭や稼働時間が限られているオフィス・店舗などと比べて、高額になりやすい傾向があります。
近年は世界情勢の影響などにより電気料金が高騰しており、多くの施設が電気代削減に努めています。
しかし、クリニックでは同様の対策を講じるのが難しいのが現状です。その理由こそが、クリニックの電気代が高くなりやすい要因でもあります。
常時稼働の空調・照明・医療機器
クリニックの電気代が高くなりやすいのは、常時稼働している機器や設備が多く存在するためです。
空調や照明、医療機器などは、患者さんや医師、看護師、その他スタッフが快適に過ごし、適切な医療処置を行うために欠かせません。
中には電源を切ることができない設備もあり、診療時間外でも稼働している施設が多くあります。入院設備のあるクリニックでは、なおさらその傾向が強いです。
また、医療機器の中には待機中でも多くの電力を消費するものがあるほか、ネットワークシステムや監視カメラなどの設備も常時稼働が必要となります。
こうした背景から、一般的な施設と比べてクリニックの電気代は高くなりやすいのです。
衛生管理・快適性維持のため節電しにくい環境
クリニックでは、衛生管理や快適性を維持するために常時稼働させなければならない設備が多く、節電が難しい傾向にあります。
特に、感染症対策として導入されている換気システムや空気清浄機、室温を一定に保つ空調設備などは、医療の質や患者さんの満足度にも関わるため、簡単に停止することができません。
こうした理由から、クリニックなどの医療施設では電気代の削減が難しいのです。
建物の老朽化や断熱性能の低さも影響
開院から年数が経過しているクリニックでは、建物の老朽化や設備の性能の低さにより、電気代が余計にかかっている可能性があります。
特に、建物の断熱性能が低い場合、空調によって室温を一定に保つためには多くのエネルギーが必要です。
外気の影響を受けやすい構造であればあるほど、エアコンなどをフル稼働させなければならず、電気代の増加につながります。
また、古いクリニックでは、老朽化した設備をそのまま使用しているケースも多く、空調設備や照明器具などが省エネ性能に優れていないことも少なくありません。
こうした性能の低い機器を使い続けることで、結果的に電気代がかさんでしまうのです。
クリニックの電気代の内訳とは?
クリニックでは節電対策が難しい傾向にありますが、どの部分で電力を多く消費しているかを把握することで、電気代削減の糸口が見つかることもあります。
多くのクリニックで電力消費の大部分を占めているのは、空調設備と照明です。これらを合わせると、クリニック全体の消費電力の約60~70%に達するとされています。
そのほか、使用していないにもかかわらず待機状態のままになっている医療機器や導入されている付帯設備などでも電力が消費されています。こうした電力使用は昼間だけでなく、夜間にも及んでいるのが実情です。
主な消費源①:空調設備(全体の約40%)
クリニックにおける電気代の中で、特に大きな割合を占めているのが空調設備による消費電力で、全体の約40%にのぼります。
特に外来診療が行われる8時から16時頃の時間帯に消費電力が集中しており、クリニックのどこにいても快適に過ごせるよう、空調が常時稼働しています。
空調設備は完全に停止することが難しいものの、運用方法を工夫することでコスト削減につなげることは可能です。
主な消費源②:照明(LED未導入の場合は30%を超えることも)
空調設備に次いで消費電力が大きいのは、クリニックの照明です。照明は全体の電力使用量の約30%を超えることもあり、特にLEDなど省エネ性能の高い照明を導入していないクリニックでは、その影響が顕著に表れます。
照明は運用方法の工夫に加え、比較的容易な設備の入れ替えによっても消費電力の見直しが可能です。まずは現在の設備状況をチェックしてみると良いでしょう。
主な消費源③:医療機器の待機電力や作動時の電力
クリニックでは、さまざまな医療機器にも電力が使用されています。これらの機器は、実際に稼働しているときだけでなく、使用していない待機中でも電力を消費するのが特徴です。
待機時の消費電力はそれほど大きくない場合もありますが、古い医療機器ほど電力消費が大きい傾向があります。
主な消費源④:給湯・換気・OA機器などの付帯設備
建物全体の設備や医療機器に加えて、クリニックではそのほかにもさまざまな機材が使用されています。
給湯設備や事務用のOA機器など、電気で稼働する機材はすべて電力を消費し、それに応じた電気代が発生します。
中には、外来診療を行っていない時間帯にも稼働しているものがあり、こうした機材によっても継続的に電気代がかかるのです。
クリニックの電気代削減で得られるメリット
クリニックで電気代を削減することは、経営面の改善だけでなく、クリニックのイメージ向上にもつながるメリットがあります。
節電対策の一つひとつは、効果を実感しにくい場合もありますが、長期的に見れば大きな影響をもたらす可能性があります。
こうしたメリットを考慮すれば、クリニック単位で節電に取り組む意義は十分にあると言えるでしょう。
経営の固定費を抑制し、利益を確保
クリニックで節電対策を行う最大のメリットは、固定費の削減によるコストカットです。
電気代は、クリニックの経費の約10~15%を占めると言われており、これを削減できれば全体の経費削減につながり、利益確保の可能性も高まります。さらに、削減した分の経費をほかの必要な分野に振り分けることも可能です。
環境配慮型クリニックとしてのブランディング向上
クリニックで節電対策を行うメリットには、クリニック全体のイメージ向上も含まれます。節電への取り組みやその成果を発信することで、環境に配慮したクリニックとして患者さんに認識される可能性があります。
これにより、自院の利益だけでなく、社会全体の利益にも貢献する存在として、より良いイメージの構築が期待できるでしょう。
スタッフの節電意識の向上で、業務効率も改善
クリニック全体で節電対策に取り組むことで、スタッフの節電意識を高めることも可能です。
「どれだけ電気代を削減したいのか」「その対策にどのような意味があるのか」といった目標や意義をスタッフ全員で共有することで、節電への意識が向上し、電気代を抑えながら業務を行う工夫が生まれるでしょう。その結果、業務全体の効率化につながる可能性もあります。
今すぐできる!クリニックの省エネ・節電対策
それでは、クリニックで取り入れやすい節電対策について見ていきましょう。
節電対策には、小規模なものから大規模なものまでさまざまあり、中には初期投資が必要となるケースもあります。ここでは、比較的低コストで始められる取り組みをご紹介します。
設備の見直し
クリニックにおける節電対策の中で、多少コストはかかるものの効果が期待できるのが「設備の見直し」です。
たとえば、特に消費電力の大きい空調や照明については、高効率な空調設備やLED照明への切り替えを検討する方法があります。
冷暖房効率が向上すれば、より少ない電力で院内の温度管理が可能です。また、LED照明は従来の白熱電球や蛍光灯に比べて消費電力が少なく、省エネ効果が高いのが特徴です。
さらに、インバータ機器や省エネ型の医療機器の導入も良いでしょう。インバータをポンプやファンに設置することでモーターの回転数を制御し、電力使用量を抑えることができます。
また、省エネ性能の高い医療機器を導入すれば、稼働時や待機時の消費電力を大幅に削減できるでしょう。
運用の最適化
なるべくコストをかけずに実施できる節電対策としては、設備の運用を最適化する方法が挙げられます。
たとえば、エアコンの設定温度や稼働時間の見直しが有効です。夏場は28℃、冬場は20℃を目安に設定し、外来診療の時間外にはできる限り稼働を停止するなどの運用により、電気代を抑えられる可能性があります。
さらに、部屋の用途に応じて細かく空調設定を調整することで、より高い効果が期待できるでしょう。
また、医療機器は待機中にも電力を消費するため、待機電力の削減も有効です。使用しない時間帯にはコンセントを抜くなどの工夫で無駄な電力消費を防げます。
そのほか、換気設備や照明の稼働時間を管理することで、さらなる節電が可能です。特に照明については、昼間に自然光を取り入れることで、不要な電力使用を抑えることができます。
見える化と電力契約の見直し
電気代の削減には、消費電力の「見える化」や電力契約の見直しも重要なポイントです。
たとえば、クリニックにデマンド監視装置を導入し、「いつ・どこで・どれだけの電気が使われているか」を可視化することで、電力使用状況を把握しやすくなります。
さらに、実際の使用状況に対して契約中の電力プランが最適かどうか、契約容量が適切かなどを再評価し、見直しの余地がないか検討することも大切です。
中長期で検討したいコスト削減策
電気代を大幅に削減するためには、より大規模な対策が必要です。このような対策は、初期費用が高額になることもありますが、中長期的な視点で見ると高い効果が期待できます。
特に、築年数の古い建物でクリニックを運営している場合は、建物全体の性能や設備の見直しを検討することをおすすめします。
建物改修時に省エネ設計を導入
築年数が古いクリニックであれば、建物の改修を検討するケースもあるでしょう。改修の際に省エネ設計を取り入れて断熱性能を高めることで、将来的な電気代の削減につながる可能性が高まります。
たとえば、屋根・床・壁といった外皮部分に断熱材を施す、窓のサッシを樹脂製に変更して複層ガラスを採用する、といった対策が挙げられます。
また、外気冷房システムや高効率ヒートポンプなどの空調設備を導入したり、空調システム全体を効率化したりすることも、電力消費の抑制に効果的です。
太陽光発電・蓄電池の導入
初期費用こそ高額ですが、太陽光発電設備や蓄電池の導入は、電気代の削減に効果的な対策の一つです。
太陽光発電を導入すれば、クリニックで使用する電力を自家発電でまかなうことが可能です。
さらに、蓄電池を併用すれば、余剰電力を蓄えておくことができ、発電量が少ない日や災害などで電力供給が停止した際にも活用できます。
これにより、電力会社から購入する電力量を抑えることができ、結果として電気代全体の削減が期待できるでしょう。
補助金・助成金を活用した設備投資
クリニックで省エネ対策を進めることで、自治体などから補助金や助成金を受け取れる可能性があります。
空調設備や照明の更新、断熱改修、エネルギー管理システム、太陽光発電設備の導入といった取り組みは、環境省・経済産業省・各自治体が実施する補助金制度の対象となることが多いです。
これらの設備投資には一定のコストがかかりますが、補助金を活用することで負担を軽減できる可能性があります。
補助金制度は、制度ごとに要件や申請期間などが異なるため、詳細については管轄の自治体に確認することをおすすめします。
まとめ
クリニックの電気代の中でも大きな割合を占めるのは、空調設備や照明にかかる費用です。これらの費用を抑えるためには、設備や運用方法の見直しが必要になります。
「株式会社データシード」の運営する統計ブログ「いちばんやさしい医療統計」では、クリニックの運用に関する情報の発信も行なっています。SDGsに積極的な会社・有益な情報をお伝えするおすすめのメディアです。
論文への医療統計の活用やSDGs達成への取り組みを取り入れたクリニック運営に関心がある方は、ぜひ「いちばんやさしい医療統計」を利用してみてください。

エコモは各地を飛び回って、電力・エネルギーや地球環境についてお勉強中なんだモ!色んな人に電気/ガスのことをお伝えし、エネルギーをもっと身近に感じてもらいたモ!
宜しければSNSでのシェアをお願い致します!