科学の専門家でない私たちは環境問題をどう考える?
所属:専修大学
インターン生:K.Iさん
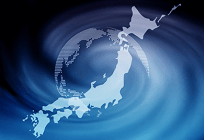
環境問題によるリスクとはどのようにもたらされたのでしょうか。環境問題は、単なる自然現象ではなく、人が作り出したリスクなのです。この記事では、環境問題が私たちの生活を脅かし、リスクとなっている、根本的な要因を考えていきたいと思います。

RAULのインターンシップに参加いただいた専修大学のK.Iさんが執筆してくれた記事だモ!内容がご参考になりましたら、ぜひともイイネやシェアしてほしいだモ!
そもそもリスクとは何でしょう。 生きていく上で、私たちの身の回りには、病気、交通事故、災害、不況、失業など、避けられない危険が様々に存在します。リスクとは、このような一般的には、リスクとは、こういった危険のことだと考えられているのではないでしょうか。
しかし、ドイツの社会学者ウルリッヒ・ベックの定義はリスクを、斬新な定義をしました。ベックは、チェルノブイリ原発事故のように、科学技術がもたらすリスクについて多く論じている人物で、東日本大震災の時に起こった福島第一原発事故の一年前に日本でも講演会を行っています。
そのベックは、著書『リスク社会』において、危険(danger)とリスク(risk)を区別し、危険とは純粋な自然災害であり、その発生に人が関係しないものであるとしました。
一方で、リスクとは、科学技術の進歩や産業開発のような、人間自身の営みや人間の選択によってもたらされるものだとしたのです。言い換えると、人間の選択によって被る可能性が生じた損害のことなのです。
その一例として、特に挙げられるのは、環境汚染や資源の枯渇です。これによって、その社会が存続していくことができなくなる可能性や、一人一人が思い描いた人生を送れなくなる可能性が生じてしまうのです。
現代はリスク社会
現代社会では、地球温暖化の影響や放射性物質の影響のように、リスクが社会の至る所に存在しています。これらは科学的に測定が難しく、人々が感覚的に知覚することも困難で、予測不可能なものなのです。
ベックは、このようなリスクが多く存在する社会のことを、リスク社会と呼びました。先に述べました通り、リスク社会をもたらしたものは、文明および科学技術の急速な発展であります。
産業革命以前の時代である中世ヨーロッパでは、科学技術がまだ飛躍的な発展を遂げておらず、自然との共生や伝統工業を、自明の前提として人々は生活を営んでいました。
そのため、急激な開発による環境破壊がもたらすリスクというのは少なかったのです。また、日本においても、明治維新以前の時代である江戸時代では、いかなる資源も余すことなく使うエコな社会が営まれていました。
それが18世紀後半になると、イギリスで産業革命が興り、科学技術の発達と経済活動の飛躍的な発展がなされます。これ以降の時代のことを、社会学では近代としています。
ベックは、近代から今日に至るまでの過程を、第一の近代と第二の近代の2つに分類しました。第一の近代とは、19世紀のような、工業を中心として経済や社会の発展を図る工業化社会のことです。
工業化社会においては、人々にとって必要だと考えられる商品を規則的に大量生産することで豊かになろうとする動きが活発になっていました。その時までは、利便性や富などの利点のみが生産され、リスクが知覚可能で確率論的に予測することが可能だったのです。そのため、この時代には保険も成立することができていました。
第二の近代とは、現代のようなリスク社会のことです。現代では、利便性のみならず、環境問題や原発事故のような負の副産物を生産されており、リスクが知覚・予測不可能なため、保険が成立させることが非常に難しくなっています。
特に大気汚染のような環境問題は、空間的にも時間的にも、影響の範囲は限定されず刻一刻と広がっていくものです。例えば、原発事故や遺伝子組み換え技術が生態系に与える影響、開発された薬物に耐性をもつ薬物耐性菌の出現、農薬に耐性を持つ生物の出現などがあげられます。こうした科学技術の影響は、良くも悪くも、人間の食糧や健康などにも未知の影響をもたらします。
ベックは、自分がしたことが自分に返ってくる自己回帰的(再帰的reflexive)な構造をもつ社会を、リスク社会と呼び、このリスクをもつ自己回帰的構造を現代の特徴としました。
この科学技術によってもたらされるリスクに対して社会はどのように対応すればよいのでしょうか。単純に、人間が経済発展を抑制したり、私たち一人一人が節約して、大量に物を消費する欲望を抑えたりすればよいのでしょうか。
あるいは、その社会でリスクを回避したり軽減したりするためにはやはり科学の力のみに頼らざるを得ないのでしょうか。たしかに、その必要はあると思われますが、それだけに頼っていたのでは問題の解決にはならないという可能性もあります。
リスク社会と科学の合理性
ベックは、リスク社会で求められるのは、科学的合理性に疑問を唱える必要があるといいます。科学的合理性とは、研究対象を数量化し表現することが可能なものだけを予測するという、科学の特徴のことです。
言い換えると、科学者が研究対象としなかったものの中に危険があったとしても、科学的合理性の中では見逃されてしまうことがあるということです。このような状況のもとでは、ある特定の危険のみを推定することとなり、科学の分野以外の要因による予想外の事態への対処は困難になり、それが問題なのではないでしょうか。
例えば、原発事故のように、目下の事故確率が極めて低いと考えられていても、一つの事故がその地域の破滅を意味するとなると、その危険性は高すぎるように思われます。
また、科学的に安全と考えられていても、予想外の人的ミスもありうるのです。つまり、こうして置き去りにされたリスクがあらゆる人々の生活や生命を脅かす可能性を常に科学合理性は孕むということであり、それこそが専門家でない人々や、科学に詳しくない人々とって問題なのであり、現代に生きる私たちの生活のみならず子孫の生活にも影響をもたらすのではないか、ということをベックは主張したのです。
そのため、ベックは、科学の問題は専門家同士や対策を任された人々のみで話し合うというような、専門主義から抜け出し、専門知識を持たない人々や、一般の近隣住民などの意見を積極的に取り入れ、多くの人々がリスクへの対処に関する議論や作業を行っていく必要性があると主張しました。
また、このような考えに基づいた合理性のことを社会的合理性といいます。有効な一例として考えられるのは、誰にでも開かれていて、互いが対等に自由に討論できる機会を増やしていくことではないでしょうか。
例えば、原子力発電環境整備機構(NUMO)は、原子力発電事業に伴い発生する「放射性廃棄物の地層処分」を実施する、日本で唯一の組織なのですが、放射性廃棄物や、その安全性について全国的な対話活動を進めています。インターネットを用いた情報発信のみならず、子どもや教育関係者、女性に焦点を当てたワークショップやセミナー、説明会など、多様な情報発信活動を進めています。
特に、NUMOも行っているような、小規模なグループで進める対話集会では、社会的合理性に基づいた話し合いで、互いに新たな問題を発見していくことができると考えられます。
そうすることで、科学に対して専門知識の少ない市民であっても、原子力発電のような専門技術に対する理解を深めながら、専門家の人たちと共に必要な対処を進めることが可能になるのだと思います。そして、万が一のリスクが不安視される場合があれば、今はまだ実施しない(予防原則)という方法もとることができます。
以上に述べてきましたように、原発事故のような科学技術がもたらすリスクの背景には、科学的合理性のみで危険を推定することが問題であるため、専門家と一般市民の人々が自由にコミュニケーションの機会をより増やしていくことで、リスクに対処した方がよい、ということが考えられます。皆さんも、興味のあることを専門家から学ぶことができますし、また、何か身の回りの生活の中で公害の問題に直面した際に、主体となって解決していくことができるのではないしょうか。
環境汚染と市民の認識に関する意外な真実
一般的には、ほとんどの人が、「環境保護は必要だと思いますか?」と問われれば、必要だと答えるのではないでしょうか。また、多くの人が、環境汚染が深刻な地域に住む人々ほど、環境保護や対策、企業の規制を望むと考えているのではないでしょうか。
しかし、近年、現実はそう単純ではない、ということが明らかになりつつあるのです。アメリカのある調査によると、環境保護の深刻な地域に住む人々ほど、環境汚染を深刻視せず、その対策の必要性も認識していないという、はたから見ると、理解しがたい心理を持っていたのです。
このような傾向は、その土地に代々暮らしてきた人々のもつ歴史や政治観、経済生活など、様々な要因が複雑に絡み合うことで生まれたものであります。ここでは、アメリカにおいて、この傾向がどのようにして生まれていったのか、アメリカにあるとある州の事例を参考に、説明してきたいと思います。
カリフォルニア大学バークレ校の社会学者のアリ―・ホックシールドという人物は、アメリカにおいて右派と左派の政治的な対立が深刻化している要因を調べていたところ、あることに気づきました。
それは、アメリカで共和党政党を支持する右派の人々が多く住む州ほど、環境汚染の危険度が高い一方で、民主的な考えに基づき政策を行う民主党を支持する左派が多くを占める州では、ということです。
アメリカにおける右派とは、保守的で排外的な思想をもって共和党という政党を支持する人たちによって構成される政治勢力のことを指し、基本的に、白人の人たちがその多くを占めています。
一方、左派とは、革新的で自由な思想を以て民主党を支持する政治勢力のことです。その右派の人たちは高確率で、大気汚染や水質汚染、土壌汚染など生活環境のあらゆるところで、高レベルの汚染にさらされて暮らしており、ガンを患いやすくなったり、土壌汚染によって地面の沈没事故に遭ったりするなどの影響を受けています。
ところが、産業公害に遭う環境など問題ではないと一蹴していたのです。これに加えて、環境保護や地球温暖化対策のために対策を講じる政府の関与や、安全点検すらも拒んでいることさえ、一般的になっていたのです。
この要因を探るために、ホックシールドは、環境汚染が深刻かつ右派の多い、ルイジアナ州レイクチャールズ市を調査対象地域として設定し、そこに暮らす住民に聞き取り調査を行いました。
その中でも特にティーパーティーと呼ばれる政治勢力に属する人々に面接形式の質問調査を行いました。ティーパーティーとは、国家の財源が、働いていない子供や高齢者などのために福祉へと投入されることに反対したり、軍事以外の分野で、政府のいかなる関与や規制も反対したりしている人々のことです。ちなみに、このような考え方をもつ人のことをポピュリストと呼びます。
彼らを調査する中で第一に明らかとなったのは、人種差別と環境破壊には関係性があった、ということです。皆さんは、環境レイシズムという言葉はご存じですか?環境レイシズムとは、環境被害とレイシズム(人種差別)が密接にかかわっている状況のことです。例えば、アメリカでは、有色人種の多い地域ほど、有害廃棄物処分場が建設されているということが分かっています。
じつはレイシズムには人種差別以外にも意味があり、「自分や、自分の属する集団と相手との違いを理由にして、その相手の価値を下げることで、自分の価値を上げる」という意味もあります。日本でも、原発労働者の多くは、貧困家庭に生まれたために生活が苦しい立場が苦しい、就業機会に恵まれかった、という人々です。
ホックシールドが調査したティーパーティーの人々は、ほとんどが白人の人たちで、差別されにくいと考えられていました。そのことがかえって彼らの陥っている状況の実態や心情が、見えにくくなっていたのです。
「差別する側である白人は恵まれた生活をしている」というレッテルを張られ、環境汚染の深刻な被害を受けてきた実態が社会でなかなか認識されなかったのです。
さらにややこしいことに、ティーパーティーの人々は、人種差別への理解を示し、自分は差別主義者ではないと考えているようでしたが、実際には無意識のうちに、差別的感情を示す行動をとっていることには気づいていなかったのです。例えば、ある墓地には、「敷地内に一本の道路が走り、白人と黒人の区域を分けていた。白人墓地の芝は最近かられたばかりのようだったが、黒人墓地の草は伸びたままだった」とホックシールドはいっています。
また、男性たちの多くは、女性や子供、高齢者といった人々に社会保障政策が行われることに否定的な考えを共通して示し、女性への差別意識を根強く持っていることが判明した。
彼らのこのような考え方は、アメリカの歴史上の転換点である、1860年代と1960年代の出来事に大きく影響を受けて形成されたものだと筆者は考察しました。1860年代、アメリカの南部では大規模区画で単一の農作物を大量生産するプランテーションが発達し、その労働力の基盤のほとんどが黒人奴隷の人々に担われていました。
これにより、小作人の白人は余分な労働力とみなされました。裕福な白人農園主は彼らに職を与え、農園主は慈愛ある白人指導者として振舞ったものの、現実に与えられた賃金は、小作人たちの生活が成り立つためにはあまりに不十分なものでありました。
これに加えて、サトウキビや綿花などの単一の食物が大規模区画で大量に育てられていたため、白人小作人たちは食料となる多様な農産物を育てるための土地すらも失い、自らの意思で必要な食料や住居を調達することができず、極貧生活を送っていました。
一方でアメリカ北部では、第二次産業革命の中で石油や電力を動力源とした重化学工業が発展し、黒人奴隷解放が政治的に正しい取り組みであるとする声が生まれ、大規模農園制度を悪だとみなして奴隷制廃止を主張する人々が登場します。
しかし、アメリカ南部では、黒人の奴隷労働力を基盤としたプランテーションで経済が成り立っていたため、奴隷解放を拒みます。この意見の対立から、南北戦争が発生し、南軍は敗北に終わりました。
1870年代になると、南部でも重化学工業が発展し、石油企業は、小作人たちに新たな雇用と繁栄と、農水産業との共存を約束します。こうして彼らは、アメリカンドリームや大金持ちになることへの期待を膨らませます。
こうして、ブルーカラー労働者へと変貌を遂げます。その中で、彼らは、特に夫が石油に関連する企業に務めることで家庭を支え、女性は家庭内で子供や高齢の親の面倒や、家事に励むことで家庭を支えるという、性別役割分業が一般的なモデルとなります。
ところが、1960年代以降、再び黒人の奴隷解放を求める動きとして公民権運動が始まり、これに刺激を受けた女性たちも、性別役割分業に基づき経済基盤を担ってきたことで抱えてきた大きな負担からの自由を求め、フェミニスト運動が始まります。
白人男性ブルーカラー労働者たちは、これを再び北部の連邦政府が政治的正しさを主張してきたかのように感じとり、自分達が人種や女性への差別主義者であるとみなされることを恐れました。
そして、1980年代にはバックラッシュという現象を巻き起こします。バックラッシュとは、フェミニスト運動の流れに反感を感じた人々が、「逆に性差別を追認し、性別役割を賛美する政治勢力が反撃を開始した」現象のことです。
つまり、父親や州民として家庭や州の経済を支えるために、マニュアル労働を担ってきたのだという誇りや、裕福になることを目指してきたことに対する名誉を求めて、北部の人がつくったアメリカ政府に反発し、環境規制も拒絶していたのです。
具体的には、彼らは、住民たちが公害を引き起こす企業を規制する政策よりもその環境規制の緩和と自由な利潤追求や競争を保護する政策を支持してきました。
州の経済や住民たちの生活は、石油化学産業を基盤として成り立ってきました。つまり、彼らのアイデンティティ、感情、考え方は、石油化学産業との密接な関わりの中で、無意識に形成されてきたのです。
そのため、たとえ公害問題が、結果的に人々の健康や安全を脅かし、経済状況の悪化をもたらすほどにまで深刻化していたとしても、石油化学産業を過剰に保護する政策を支持する考えをもっているというのは、ある意味では必然の流れであったのです。
また、1620年代、相次いでアメリカへと移住したピルグリムファーザーズの宗教思想、ピューリタニズムも、右派の考え方の背景となっていました。ピューリタニズムのもつ思想とは、安全な生活や利潤のためではなく、神から与えられた天職や使命を果たし、救済されることを目的として働くという労働観を持つというものです。
このような思想のもと、子孫たちは産業を発達させ、職務を果たすべく勤勉に働いてきたのです。その予想外の結果として、環境汚染が発生し、不利益を被るようになったのです。
そして、このような過程で、環境対策のような職務遂行以外の行動は目的にそぐわないとする考えも強化されていった、ということになります。 それゆえに、ティーパーティーの人たちは、環境被害を受けてもその対策をすることは天職を果たすという目的にそぐわないため、「耐え忍ぶことこそが美徳だ」「アメリカ人らしい考えだ」といった心理的な傾向を無意識に形成していったのです。
この傾向は、経済的・政治的に有力な権力者が、経済成長による解決や、経済的成功といたアメリカンドリームを労働者にみせ、経済の活性化や、不況からの脱出を図ろうとする中で、さらに強まりました。
こうして、事故を起こして住民に被害をもたらした石油化学企業の責任も見過ごされていってしまったのです。また、このような資本主義体制のもとで資本家は、州の政策方針である環境規制緩和の恩恵を受け、あらゆる規制から免れることができるため、ティーパーティーの人々はますます忍耐と労働が求められ、生活力は損なわれていく中で、環境汚染や事故の責任を明確に認識することができなくなっていきました。その結果、右派の州民たちの多くが、安全な住居や必要な教育、医療サービスなど多様な公的福祉サービスから遠ざかってしまうこととなります。
その上、ティーパーティーは、社会全体の構造からもたらされたリスクを自己責任として引き受け、その克服を彼らのコミュニティへの忠誠心・リスクを冒す勇気・逆境から立ち直る力・利他的行動によって果たそうとしました。これにより、福祉や環境保護規制の必要性についての認識はより歪められることとなり、彼らは自分たちに必要な政策を拒絶するようになっていきました。
つまり、右派の考えの根拠となっているとされていた利己主義、人種的偏見、同性愛嫌悪、救貧の拒絶は、右派の政策を支持する直接的な根拠ではなかったということとなります。
加えて、彼らはこのような考えを、家族や近隣住民との個人的付き合いの中で、確信を深めていきます。互いに同じような考え方を持つ人々を、自分の判断が正しいことの根拠にする傾向が、人間には備わっているのです。
このような判断の相互依存の過程に置かれていると、人は自分や知人の判断が仮に間違っていたとしても容易に肯定し、互いに同じ判断の確信を深め合ってしまいます。
これにより、極端かつ不合理で保守的かつ偏見に満ちた考えを持つ傾向(経路的依存性)が生じます。こうして、右派政党を支持する集団の活動に熱心な人々、つまりはティーパーティーに属している人は、自分達とは異なる考え方に基づく環境政策を異質なものとみなし、排除しようする傾向が高いのです。
このような傾向は、さらに、テレビ番組によって助長されました。テレビ番組は、視聴者を確実に獲得するために、右派か左派に標的を絞って、それぞれに聞こえの良い情報を発信することとなります。
これにより、右派はより一層、自らの考えに確信を深めていきました。また、石油会社や政治家も、自らの権益に優位に働くようにメディアの報道や政治活動、法律の策定に働きかけるため、さらにこの傾向には拍車がかかります。これに加えて、このような事情に気づかないまま州政府は環境規制や安全対策を進めたため、必要な政策に対する住民の理解を得られず、むしろかえって反発が強まったのです。
それでもティーパーティーは、活気に満ちたコミュニティ生活・完全雇用、自分達の職業の尊厳、自由、良い収入や、そして環境保護も依然として望んでいます。
ですが、問題は、彼らの支持する共和党政権の政策では、実現できない可能性が高いということです。この問題には、現代では、ロボットなどによる生産の自動化が進んでいることや、グローバル化により進出した多国籍企業が、より安い賃金で働く人の多い地域で人材を雇用していることと関係しています。
つまり、場所による人件費の差を利用して利潤を生み出す企業が増加し、一見して雇用率が増加した一方で、低賃金のマニュアル労働で貧困に陥る人々が増加するという事態が発生していたのです。
ところが、ティーパーティーや州政府はこのような現状にもかかわらず、その解決策として多国籍企業ないしはグローバル企業を招致する方針を掲げ、この方針に基づく法整備を支持しました。
そして、低い賃金水準や低い労働組合の組織率を保てるように労働権法の制定を行ったり、州外や国外に本拠地を置く企業のために、法人税を安くしたり、税金から拠出した高額の助成金を与えてインセンティブとしたりすることで、経済回復と貿易輸出額の増加を図ったのです。これにより、雇用率が表面的に改善されるのみの結果となり、ルイジアナ州の市民の支払った税金が州外へ流出しました。
その上、多国籍企業や資本家は、労働者がもたらした剰余価値や利潤の多くを自らの利益し、福利厚生として活用することはありませんでした。そのため、一層、州の財政は停滞・悪化の一途をたどり、多くの従業員や住民が困窮していくこととなりました。
ブルーカラー労働者は企業に忠誠を尽くす一生を送ってもその恩恵は彼らに還元されず、景気も改善されることもなく、税金を支払っても正常に公的サービスを得られないという状況に陥りました。
この解決策として、この問題を突き止めたホックシールドは、共和党政権の政策ではなく、リベラル左派の多いカリフォルニア州の戦略に倣い、全ての人が人種や性別に関係なく教育や公共設備を利用できるような政策をとることで、新しい技術や産業の開発を促進する必要があると述べました。これにより、既存の産業システムや男性を稼ぎ主とした伝統的な性別役割分業に頼らない経済を発展させることができると考えたのです。
また、現代アメリカの福祉制度は、原則としてリスク管理に対する責任を、個人に求めており、問題解決は市場を中心とした方法をとっています。つまり、この構造が問題なのであり、他の体制へと転換する必要性を強調したのです。
その一例として、北欧諸国の政府がとっている政策のように、全ての国民が社会保障を受ける権利を持っているのだと捉え直すことで、リスクの社会的包括が可能になると考えたのです。
以上に述べてきたような社会学者のA.R.ホックシールドの研究からは、互いに異なる考え方を持ち、異なる歴史的背景や葛藤があったとしても、互いの立場になって共通点を知る努力を重ねることで深い洞察が可能になり、目前の問題解決につながる可能性も広がるのだということが示唆されたのです。


