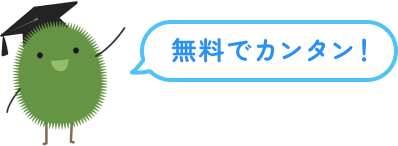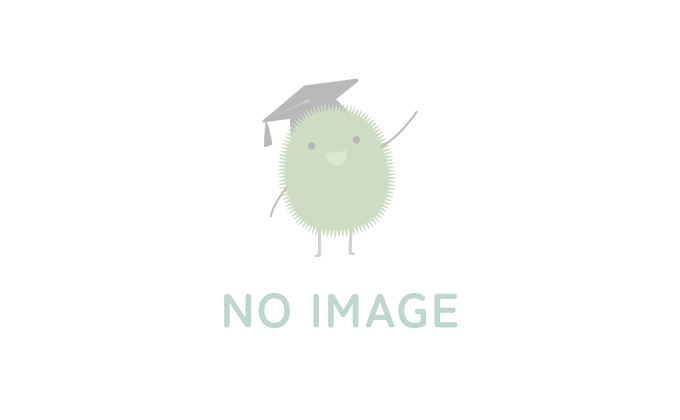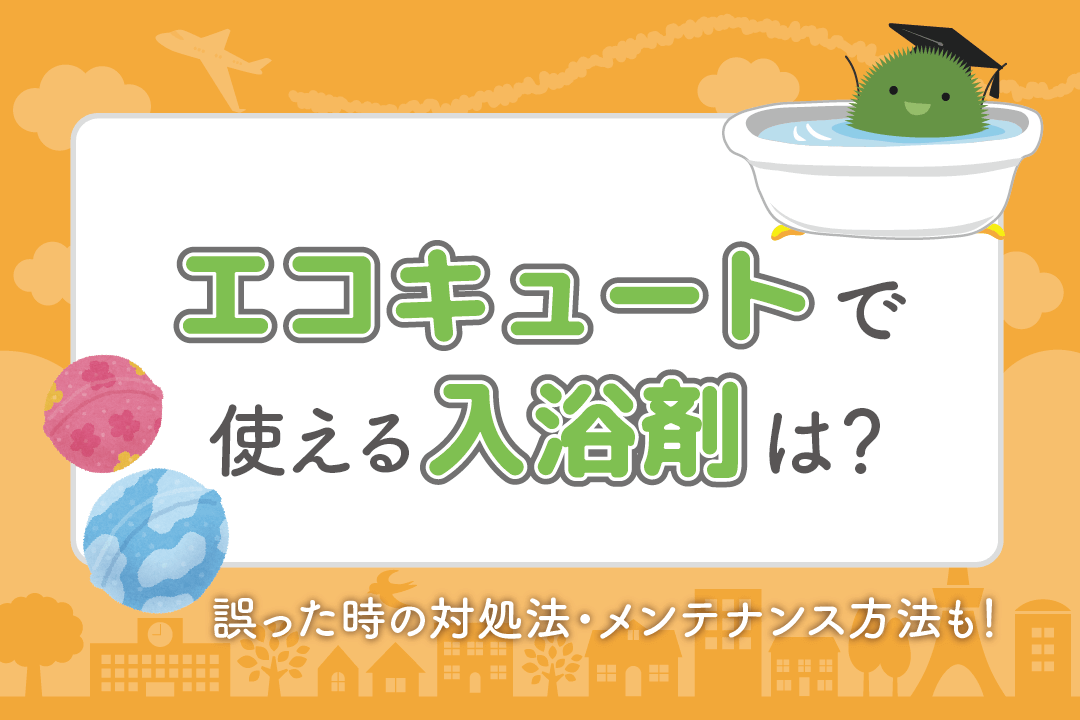日本の環境問題 どう解決する?
所属:武蔵野大学
インターン生:K.Sさん

近年、環境問題が各メディアで取りざたされる機会が増えてきています。また、深刻化する環境問題に大なり小なり危機感を覚えているでしょう。では、日本の環境問題は、現状どうなっているのでしょうか。また、それらの対策に日本はどの様な政策を行っているのでしょうか。そして、問題を解決するための糸口を考えていきましょう。
環境問題の原因は?
環境問題とは、人間活動によって引き起こされる自然環境の変化や破壊が原因で、生態系や人間の健康、社会経済に悪影響を及ぼす問題のことを指します。主な例を挙げると、
- 火力発電や工場の温室効果ガスの排出による地球温暖化や大気汚染
- 産業廃水や生活排水による海や川の水質汚染
- 木材の大量消費や開墾などを目的とする過剰な伐採による森林破壊
- 廃棄物が海に流れることによる海洋汚染
などがあります。すべてに共通して人間の経済活動が関係しています。
日本の環境問題の現状
地球温暖化
近年、地球温暖化の影響が世界中で指摘されています。また、温暖化に伴う異常気象も相次いで起こっています。 日本でもほぼ毎年、大規模な気象災害が発生しています。そして、全国に甚大な被害をもたらしています。地球温暖化の原因は、人為起源の温室効果ガスだろうと考えられてきました。
しかし、2021年8月には「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の総会で承認された第6次評価報告書の第1作業部会報告書の政策立案者向けの概要(SPM)では、「人間の影響が大気、海洋、陸地の温暖化を引き起こしていることに疑いの余地はありません。」と記載されました。ここで初めて、人間の活動が地球温暖化の原因となったっていると断言されました。
このような状況において、気候変動は喫緊の課題となっています。パリ協定の段階では、平均気温の上昇を2℃に抑えることを、必ず達成し、さらに気温を1.5℃以下に保つ努力を継続することを目指しています。
2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、二酸化炭素以外も含む温室効果ガスの全てを網羅し、新たな2030年度目標の裏付けとなる対策・施策を記載して新目標実現への道筋を描いた「地球温暖化対策計画」と2050年カーボンニュートラルに向けた基本的考え方、ビジョン等を示した「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」等の改定を行いました。このまま温暖化が続けば、気候の大幅な変動によって異常気象の頻発や高潮による洪水、干ばつによる農業の停滞、食糧不足など甚大な影響を及ぼすと考えられています。そのため、これらの計画や戦略を実現していく必要があります。
水質汚染
日本はもちろん世界中のさまざまな場所で水質汚染が問題となっています。日本の水質汚染による事件で、水俣病やイタイイタイ病など現在に続く公害病が大きく取り上げられることが多々あります。しかし現在では、過去に大きな事件があったからこそ、法律の整備が行われ規制が強化されました。故に、産業排水による水質汚染は非常に少なくなってきました。
一方で、生活排水に関する規制が定まっておらず、それによる水質汚染が問題になっています。生活排水とは、台所やトイレ、風呂、洗濯など、日常生活で発生する排水のことを指します。水質汚染は、水棲生物やそれを捕食している多くの野生生物などの生態系に深刻な影響を与えています。水質汚染によって、水棲生物が減少すれば捕食している生物も餌が取れなくなり、捕食生物までもが減少するためです。
結果的に多くの野生生物が絶滅の危機に追い込まれ、生物の多様性をも阻害する要因になります。また、水質汚染は、人間の生活に必要な水資源の減少にもつながる重大な問題とも言えます。魚介類などの海産物獲得量減少による、食の問題にも影響は大きく現れます。つまり、水質汚染の改善は生態系の維持をするだけではなく、世界中の人々の食生活にも関わる重要な課題のひとつです。
水質汚染は、人々の健康をおびやかす問題にも直結します。例えば、水質汚染が進むことで不衛生な水環境へとつながり、汚染された水を飲料水として摂取すると健康被害を引き起こす可能性があります。現在でも一部の途上国などでは、水道施設や浄化施設の整備が進んでおらず、重篤な感染症を引き起こす原因となっています。手洗いなどの基本的な衛生対策を行うには安全な水が必要であり、水道設備や浄化施設の整備は健康維持にも欠かせないものです。健康被害を防ぎ、安全な水の安定供給を実現するためには、生活排水を可能な限りきれいな状態で流す必要があります。
海洋汚染
海洋汚染と聞いて、まず真っ先に思い浮かべるものは「マイクロプラスチック問題」だと考えます。実際、海洋ごみの中でも特に深刻なのは海洋プラスチックごみです。他にも海を汚染し、生物や環境に多大な影響を与えるものは多く、人の日常の暮らしから発生したものばかりです。
海洋ごみは年々増え続けており、このまま何の対策も行わなければ2050年には海洋に住む魚などの生物よりもごみの方が多くなると言われています。陸域で発生したマイクロプラスチックは、大きなプラスチックごみと共に河川を通して海洋に流入します。大きなプラスチックごみは、一旦海岸に打ち上げられるか、浮遊している間に紫外線と物理的な力で細かくなっていきます。海洋に流入したプラスチックの大半は、海底堆積物に蓄積する結果となります。
プラスチックの多くは海水より比重が小さいが、生物膜の付着により比重が大きくなることに伴う沈降や生物の糞便への取込により堆積物に蓄積します。東京湾における 0.3~1 mm のサイズのポリエチレンマイクロプラスチックについての収支計算では、東京湾に流入したマイクロプラスチックのうち,92~98%が湾内に堆積し、2~8%が湾外へ排出されると見積もられました。プラスチックゴミは、不溶性の人工物であるために一度海洋に流入すると何百年と海洋環境を脅かします。
また、マイクロプラスチックは海洋の生態系に侵入し、食物連鎖の過程で人間に悪影響を及ぼす可能性も懸念されています。日本では、循環型社会形成推進基本法に基づいて、循環型社会を作り上げていくための施策を総合的に、計画的に推進するための第4次循環型社会形成推進基本計画や、海洋プラスチックごみ対策アクションプランという、プラスチックの有効利用を前提としつつ、プラスチックごみの回収から適正処理を徹底するとともに、ポイ捨てや不法投棄、非意図的な海洋流出の防止を進めています。これらは、政府だけでなく関係機関、地方自治体、漁業関係者などと連携した海洋環境改善のための計画です。
大気汚染
大気汚染とは、車の排気ガスや工場から排出される煙などの有害物質によって空気が汚れてしまう現象のことです。まれに火山の噴火や砂嵐などの自然現象が原因で大気中に有害物質が発生するケースもありますが、大半は人為的な活動が原因となっています。大気汚染の主な原因物質は6つあります。
微粒子状物質
微小粒子状物質(PM2.5)は粒子の大きさが非常に小さい(髪の毛の太さの 30 分の 1)ため、肺の奥深くまで入りやすく、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患への影響のほか、肺がんのリスクの上昇や循環器系への影響も懸念されています。
光化学オキシダント
オキシダント濃度が高くなると、目やのどに刺激を与え、目がチカチカする、のどが痛い等の症状がみられることがあります。
二酸化窒素
目、気管支、肺胸部の呼吸器系を刺激し障がいを起こします。
浮遊粒子状物質
粒子状物質とは、固体及び液体の粒子の総称であり、粒径10μm以下の浮遊するものを特に浮遊粒子状物質(SPM)と呼びます。肺や気管等に沈着するなど、呼吸器への影響があります。
二酸化硫黄
目には見えませんが、鼻を突くようなにおいがあり、せきや喘息、呼吸困難を起こしたり、酸性雨となって植物を枯らしたりすることもあります。
一酸化炭素
血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害するなど影響を及ぼすほか、温室効果ガスである大気中のメタンの寿命を長くすることが知られています。
大気汚染問題とは、人間の経済・社会活動によって、大気中の微粒子や有害な気体成分が増加し、環境や人体に影響を与える一連の問題を指します。日本では特に、光化学オキシダントについて、大気汚染対策と気候変動対策の両面から対策が必要であるとし、令和4年1月、「気候変動対策・大気環境改善のための光化学オキシダント総合対策について〈光化学オキシダント対策ワーキングプラン〉」を策定しました。
森林破壊
日本は、国土の約67%が森林であり、その中の30%が人工林です。温暖で湿潤な気候であり、緑が豊かな国のひとつだと言えます。世界では、森林率を見てみると1990年→2020年で1.4%減少しています。あまり多くないと感じますが、森林面積は約1億5,000ヘクタール以上失われ、毎年平均592万ヘクタール失われたということになります。
日本ではそれほど過剰な森林の伐採はなされていません。日本は木材輸入自由化を経て、利用する木材の80%が輸入されるようになりました。そのため、放置された人工林が、密生し必要以上に生い茂ってしまうと、地面付近に太陽光が届かなくなってしまい、森林本来が持つ生物保全や水源涵養機能などが失われていることが問題視されています。
そのため、資源として活用できる程度に木が成長した際には、適切に伐採し木材として有効に活用することが、未来の地球環境のためになると言えます。また、外国産木材を低価格で輸入しているので間接的な森林破壊に加担しています。日本政府は2001年4月から「グリーン購入法」、2017年から「グリーンウッド法」を施行しました。
グリーン購入法
製品やサービスを購入する際に、公的機関が率先して環境への負担の少ない商品を選んで購入するための法律
グリーンウッド法
伐採国で合法に伐採された木材の流通を促進することで木材の違法伐採を抑制するための法律
解決のために
ライフサイクルアセスメント
本記事では、環境問題を解決するための方法の一つとして、ライフサイクルアセスメント(LCA)を紹介します。LCAは、対象とする製品を生み出す資源の採掘から素材製造、生産だけでなく、製品の使用・廃棄段階まで、ライフサイクル全体(ゆりかごから墓場まで)を考慮し、資源消費量や排出物量を計量するとともに、その環境への影響を評価する手法です。
実際にみえている製品やサービスの使用段階での環境影響だけでなく、製品が製造されるまで、また廃棄に至るまで、目に見えないところでの環境影響を考えることが特徴的です。つまり、製品やサービスがそのライフサイクルで及ぼす環境負荷を評価することができる点で、環境問題の解決に非常に有用であることが分かります。例えば、ある製品の評価を行った際に、資源調達段階で大きな環境負荷がかかっていることが分かれば、それをリサイクル資源に置き換えるなどの対策が立てられます。
LCAの手順
1.目的及び調査範囲の設定
何のために対象を評価するのか目的を決め、その目的に応じて、どの程度の詳細さ、範囲でLCA を実施するかを決定します。
2.インベントリ分析
対象製品のライフサイクルで環境から採取した資源量、エネルギー量等のインプット、環境へ排出した物質(CO2等)のアウトプットを計算します。
3.影響評価
環境への影響(地球温暖化、生物多様性等)を評価する。場合によっては、それらを統合して、一つの指標で表します。
4.解釈
今までの計算の結果を精査し、結論としていえることを明確にします。目的にそぐわない場合は、再度1~3をやり直します。
5.クリティカルレビュー
第三者の専門家に評価してもらい、LCA報告書の信頼性を向上させます。LCAをするうえで、明確な国際規格の存在は、評価者にとって心強いものです。その一方で、ISOを知らなければ、全てのLCAはエセLCAになる危険性をはらんでいるともいえます。
そのため、しっかりしたLCA結果を公表したいときには、必ずISOのルールを知識として持つ必要があります。また、ISOで定められたLCAの手順には、主観的な基準が多く存在します。適量がどの程度かは評価者の「エキスパートジャッジ」にゆだねられているのです。これらが、LCAには高い専門性が必要であると言われる所以です。人によっては計算結果が3倍も10倍も変わってしまうことになるのです。ただ、このようなISOの規格が存在していることを知っているだけでも大きな価値です。
システム思考
システム思考とは、さまざまな要因のつながりと相互作用を理解することで、真の変化を作り出すためのアプローチです。その特徴として、物事のつながりや関係性に着目できる点や、ものごとの本質を理解し問題の解決策を考えることができる点が挙げられます。システム思考のツールは、2つあります。
氷山モデル
氷山モデルとは、システムの全体像を氷山にたとえ、私たちが魅惑されがちな「できごと」は海面上につきだしている氷山の一角に過ぎず、海面下の目に見えにくいところに「パターン」「構造」「意識・無意識の前提(メンタル・モデル」があるとするシステム思考のフレームワークです。
ループ図
ループ図とは、関心のあるシステムの主要な要素及びそれらに影響を与える要素、影響を受ける要素を列挙し、要素間の因果関係を矢印で結びながら、要素間の相互作用の構造を図式化するためのツールです。ループ図には、どんどん1つの方向に向かって増加または減少していく(正のフィードバック)自己強化型ループと、あるところで収束したり、ある幅で安定を保ったりするバランス型ループがあります。
システム思考で特質すべき点は、レバレッジ・ポイントと呼ばれる、システムの中で「より少ないリソースでより大きく持続的な成果をもたらす介入場所」を探すことです。つまり、システムの全体像を希求し奥深くにある本質を探すことで、少ない労力で大きな成果が得られる可能性があるということです。環境問題はその規模の大きさから、根本的な原因の究明や発生したそばから解決することは非常に困難です。つまり、システム思考によってレバレッジ・ポイントを見つけることができれば、環境問題を改善することが可能であるということです。
まとめ
環境問題は知っていても、その対策として日本が何をやっているのかを知っている人は少ないでしょう。本記事で紹介した政策は、全体のほんの一部です。また、ライフサイクルアセスメントやシステム思考も問題解決へのアプローチの一種であるために、探っていけば環境問題の解決策はいくらでもあります。この記事を読んで、少しでも日本の環境問題の現状を知ってもらい、関心を持って頂ければ幸いです。そして、より環境に配慮した生活が普及すれば良いなと思います。
宜しければSNSでのシェアをお願い致します!