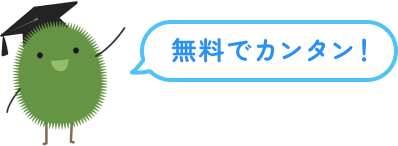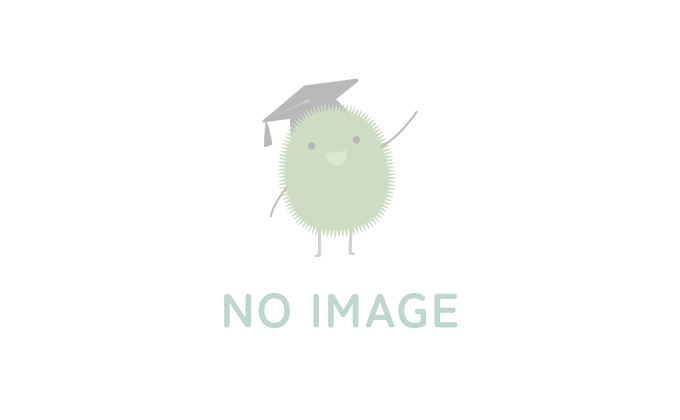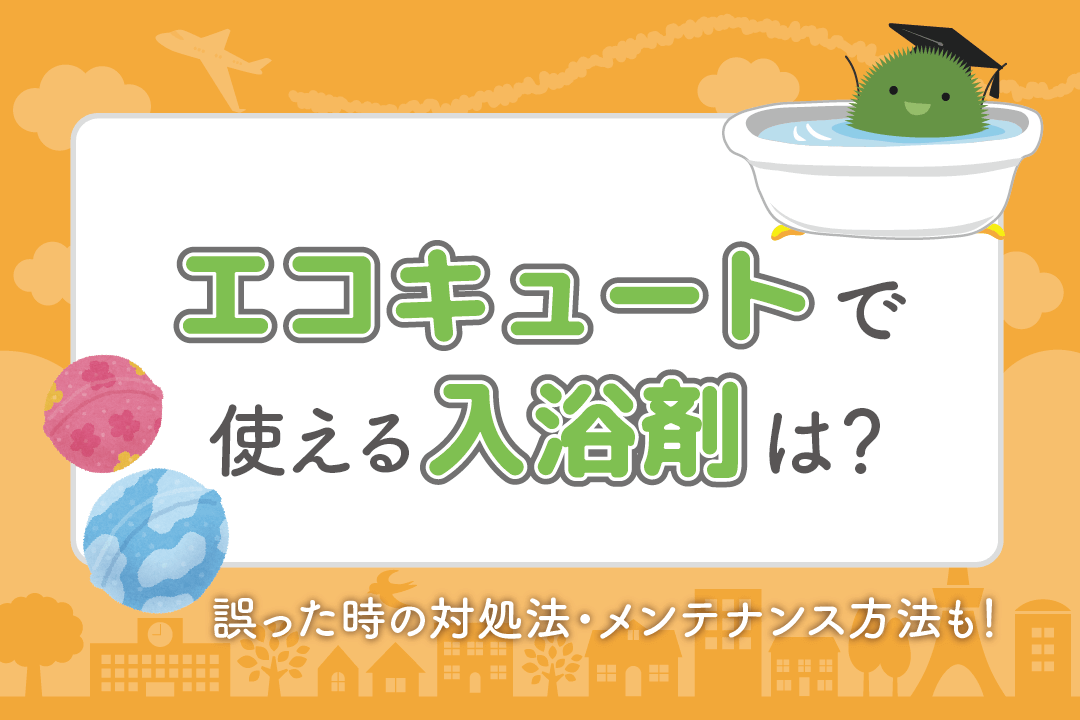地球温暖化から野生動物を守るために
所属:跡見学園女子大学
インターン生:R.Wさん

みなさんは、海の上で流氷に取り残されているシロクマを見たことがありますか?あれは地球温暖化の影響により行き場をなくしてしまったシロクマです。現在、私たちの生活を日々脅かしている「地球温暖化」。そんな地球温暖化の影響を大きく受けているのは私たち人間だけではありません。たくさんの野生動物も深刻な被害を受けています。今回はそんな野生動物の観点から地球温暖化について理解し、野生動物を救うためにこの記事を読んで今一度自分の生活を見直してみませんか。
地球温暖化は人間のせい?!
学校の授業やテレビや新聞などで「地球温暖化」という言葉を一度は見たり、聞いたりしたことがあると思います。近年、世界中では地球温暖化により多くの被害が出ています。世界各地では大規模な森林火災や豪雨、洪水、猛暑といった異常気象など様々な被害が出ています。そんな地球温暖化ですが、地球温暖化はなぜ起きているのか、どのような影響が出ているのか詳しく知らない人も多いと思います。なので今回はまず、そもそも地球温暖化はなぜ起きているのかということについて詳しく解説していきます。
私たちが住む地球は、太陽の熱で暖められており、暖められた地表からは熱が放出され、その一部は宇宙に放出されています。しかし、大気中に二酸化炭素やメタンなどの温室効果ガスが増加すると、今まで以上に熱を吸収してしまいます。その結果、大気が徐々に暖まってしまい、地球温暖化が起きてしまいます。ではなぜ、大気中に温室効果ガスが増加してしまっているのか。
それは1850年前までさかのぼります。1850年以降、イギリスで産業革命が起きたことにより社会はどんどん発展していきました。人間が、石炭を掘り出して燃やし、エネルギーを作り出したことで人類の生活は豊かになりましたが、石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料を燃焼させたことで二酸化炭素の排出量は増えてしまったのです。そして、結果的に1850年以降から世界の平均気温は上昇し続けています。
今や私たちの生活に欠かせない、エアコンやテレビ、冷蔵庫、洗濯機。それらを使用するための電気を作る時には、大量の化石燃料が使われており、大量の二酸化炭素が排出されています。特に、自動車は化石燃料であるガソリンや軽油などの燃料を燃やしているので、大量の二酸化炭素や一酸化炭素が排出されており、環境に大きな悪影響を及ぼしています。それにより、世界ではガソリン車の廃止が進められており、電気自動車に移行していくメーカーが増えています。また、熱帯雨林などの森林は二酸化炭素を吸収し、酸素を排出してくれていますが農地の拡大などにより森林伐採が行われ、どんどん失われてしまっています。森林が減少し、森林からの二酸化炭素の吸収量が減少してしまったことも温室効果ガスが増加し続けている原因となっています。
ここまで説明してきた、産業革命、家電製品や自動車の利用、森林伐採は全て人間の手によって行われたことです。そして、IPCCの第6次評価報告書によると「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」と初めて断定する報告が公表されました。つまり、地球温暖化が進んでしまっている主な原因は、私たち人間の活動によるものなのです。
地球温暖化の被害を受けている動物
地球温暖化で被害に遭っているのは人間だけではありません。実は、私たちと一緒に住んでいる動物にも影響を与えています。現在、IUCN(国際自然保護連合)が発表している、世界の絶滅の恐れがあるとされている野生動物のリスト「レッドリスト」(2020年公表)には、約3万8000種以上の野生動物が絶滅危惧種として掲載されています。
その中でも地球温暖化の影響を受けていると考えられている絶滅危惧種は、2000年以降増加しており、2020年には4000種を超えました。生息地の変化や干ばつ、気温上昇・低下、暴風雨、洪水などによって影響を受けています。絶滅危惧種のうち地球温暖化の影響を受けている動物の種類の割合は、鳥類が最も多く、全体の約33%が影響を受けています。次に無脊椎動物が多く、全体の約32%が影響を受けています。最も影響を受けていないものは、爬虫類で影響を受けているのは全体の約8%です。
そして、気候が変化すると採れなくなる食物も出てくるので、エサが減ることで繁殖が出来なくなり、数が減少してしまう動物が出てきます。それと同時に、生息地を広げて数を増やす動物も出てくるでしょう。このように生態系が変化することで、現在は地球温暖化の影響を受けていない動物もやがて影響が出てくる恐れがあります。
地球温暖化の影響を受けている野生動物の例
実際に地球温暖化の影響を受けている野生動物は数多くいますが、今回はその中から絶滅危惧種として懸念されている動物をいくつか紹介します。
ホッキョクグマ
まず初めに紹介する動物はホッキョクグマです。ホッキョクグマは「シロクマ」とも呼ばれて親しまれており、好きな方も多いのではないでしょうか。ホッキョクグマは陸で生活する動物ですが、ほとんどを氷で覆われた海の上で過ごします。成長したホッキョクグマは厳しい寒さに耐えるために、脂肪の多いアザラシの赤ちゃんを好んで食べます。夏になると流氷が多くなり、陸地で暮らさなければならないため、春のうちに多くの脂肪を取っておくことが生存確率向上や繁殖の成功につながります。
そんなホッキョクグマですが現在、地球温暖化の影響により住処が脅かされつつあります。北極圏の氷は気温上昇の影響を受け、春に解けだす時期が早くなり、再び秋に凍結するのが遅くなっています。さらに氷の厚さも薄くなりました。このまま地球温暖化が進むと2025年には北極の氷結面積が1900年代の80%に減少すると予想されています。
先ほども説明したように、ホッキョクグマは生命が維持できるように春のうちに栄養を蓄えなければならないため、氷の解けだす時期が早まれば、それに合わせて陸地に移動しなければなくなり、狩りの出来る期間が縮まってしまいます。すると、栄養不足により体重が軽くなり、体力も落ちてきてしまうので繁殖にも影響が出てしまい、ホッキョクグマの総個体数がどんどん減少してしまいます。
コアラ
オーストラリアの森林に生息するコアラ。木につかまっている姿なんか癒されますよね。コアラはカンガルーと同じ有袋類と呼ばれる哺乳類の一種です。基本は単独で樹の上で生活していますが、日陰を探すなどで地面に降りてくることもあります。主な食物はユーカリの葉ですが、ユーカリの葉にはタンニンなどの毒が含まれており、栄養価も高いためこれを食べる動物はあまりいません。しかし、コアラはユーカリの葉を分解し、消化する微生物を体内に保持しているため食べることが出来ます。また、コアラは水を飲みません。ユーカリの葉は約55%が水で出来ており、生きるために必要な水分をユーカリの葉で供給しているからです。
そんなコアラは1990年代以降、地球温暖化の影響による干ばつや大規模な森林火災で食べ物を失ったり、住処をなくしたりしています。干ばつにより、ユーカリの森を広く枯渇させてしまい、コアラが水不足に陥って衰弱死してしまう例が増加したといわれています。また、大規模な森林火災では多くのコアラが火傷などのケガを負ったり、命を落としたりしました。生き残ったコアラも住処をなくしたことで減少や絶滅の危機が心配されています。コアラの生息地ではもともと落雷などにより森林火災が起きていましたが、通常は雨で自然に鎮火するので問題にはなりませんでした。しかし、熱波や雨不足などの異常気象により、被害を拡大させることとなってしまったのです。
ユキヒョウ
ユキヒョウは、アルタイ山脈を始めとする標高数千メートルの山岳地帯に生息する大型のネコ科動物です。人間がほとんど踏み入れることがない場所に生息しているため、ひと昔前までは「幻の動物」と言われていました。岩穴に住み、シカやヒツジの仲間、ウサギなどを捕食しています。体の大きさは100cm~149cmほどで、体重は40~50kgほどです。体には長いモフモフの毛が生えており、雪や氷で滑ることを防いでいます。また、一般的なヒョウは人を襲うことがありますが、ユキヒョウは人を襲いません。
そんなユキヒョウもまた地球温暖化の脅威にさらされています。現在は約2700~3300頭いるユキヒョウですが、地球温暖化による生息地の環境変化などにより、ユキヒョウの生息数は一時期1000頭ほどにまで激減しました。
アオウミガメ
アオウミガメは熱帯から亜寒帯にかけての海域に広く生息するウミガメの一種です。最大で1.5メートルほどまで成長し、ウミガメの中では最も大きな種類です。アオウミガメは草食性であり、アマモやウミヒルモなどの海藻を食べています。また、産卵場所は幅広いため、現在ではほかの種が産卵を行わなくなってしまった太平洋中央部の島々でも産卵を行っています。一度の産卵で100個以上の卵を産みますが、人間による卵の捕獲が後を断ちません。
そんなアオウミガメは1980年代から絶滅の危機が懸念されていました。原因は人間による食用や商用にするための卵の乱獲や海洋汚染、産卵場所の砂浜や海草藻場の開発などです。そして近年、地球温暖化による深刻な問題が指摘されています。ウミガメは産み落とされた卵を取り巻く砂の温度が約29度よりも高ければメスが生まれやすく、低ければオスが生まれやすくなっています。なので地球温暖化により温度が上昇してしまうとメスが多く生まれるようになり、オスとメスの比率が偏ってしまい、継続的な繁殖が難しくなってしまいます。
野生動物を守るために私たちが出来ること
ここまで地球温暖化の影響を受け、絶滅危惧種として懸念されている野生動物を紹介してきました。続いて、そのような野生動物を守るために私たちが出来ることについて紹介します。
地球温暖化について良く知る
物事を解決するにはまず、現状を知ることが大切です。地球温暖化について知っているつもりでも知識不足であったり、インターネットで誤った情報を信じてしまったりしているかもしれません。しかし、温暖化の現状はかなり深刻です。地球温暖化はなぜ起きているのか、どんな影響が出ているのか、このまま温暖化が進むとどうなるのか、などから知っていきましょう。そのうえで自分はこれからどうしたら良いのか考えましょう。
地球の危機を周りの人に発信する
地球温暖化について学んだら、情報を自分の中で留めておくのではなく、知ったことや考えたことを周りの人にも伝えることが大切です。そして、より多くに人に危機感を感じてもらいましょう。伝える手段はどんな形でも構いません。直接話す、SNSで発信するなど自分が取り組みやすい方法でしていきましょう。特にSNSはより多くの人に発信できるので良いかもしれません。また、SNSは普段あまり新聞やテレビのニュースを見ない若者も利用しているので、より幅広い世代に伝えることが出来ます。そうして、すこしずつ地球温暖化に関心のある人を増やし、大勢で声を上げていきましょう。
普段の生活を少しづつ変えてみる
地球温暖化は私たち人間の行いで進んでいます。なので、地球温暖化を防ぐには私たちの生活習慣を変えていかなくてはなりません。ここで私たちにも出来る例をいくつか紹介したいと思います。
- 移動手段を徒歩や自転車、または交通機関に変える
- 使用していないコンセントは抜く
- 冷房の設定温度を上げる
- 環境にやさしい製品を買う
- 電化製品は省エネ製品を選ぶ
- 電気自動車に乗り換える
- リフューズ、リデュース、リユース、リサイクルをする
- 誰もいない部屋は電気を消す
- 買い物はマイバックを持参する
以上のように、すぐに取り組めることはたくさんあると思います。まずは自分に出来ることからすこしずつ実現していきましょう。
地域の地球温暖化対策に参加する
各自治体では地球温暖化防止の取り組みを行っているところがあります。もしかしたらあなたの住んでいる街でも何かしているかもしれません。実際に地域のボランティアやイベントに参加してみることで、新たな発見や課題が見つかるかもしれません。また、同じ志を持った仲間に出会え、自分が活動する意欲にもつながります。
地域や団体による地球温暖化防止の取り組み
最後に地域や団体活動で行っている取り組みを紹介したいと思います。
長野市地球温暖化防止活動推進センター 『親子環境バスツアー「温暖化ってなあに?」』
夏休みの親子(小中学生)を対象とし、環境施設の見学や自然観察会を通して地球温暖化について学び、自ら考え、行動を起こす機会となることを目的としたバスツアーです。
徳島県地球温暖化防止活動推進センター 『ふるさとカーニバル阿波の狸まつり啓発事業』
「COOL CHOICE」を理解し、地球温暖化対策に努める県民の増加を目的として行われました。「ふるさとカーニバル阿波の狸まつり」は徳島県のエコイベントであり、学生推進員とともにブースを出展し、「COOL CHOICE」の普及啓発を行いました。
「COOL CHOICE」とは政府が実施している国民運動であり、2030年度の温室効果ガスの排出量を2013年度比で26%削減するという目標を達成するために、省エネや低炭素型の製品、サービス、行動などにおいて賢い選択を促す取り組みです。省エネ家電にする、電気自動車を買う、公共交通機関を利用するなどが例です。
兵庫県神戸市 『公共交通の利用促進でCO2削減しながら子育て世帯を支援』
自家用車の利用を減らし、公共交通の利用を促す取り組みとして、子供の運賃は大人が同伴する場合に大人一人につき小学生以下2人まで市のバス・地下鉄の料金を無料にしました。これには公共交通の利用を促すとともに、将来の乗客となる子供に幼いころからバスや地下鉄に慣れ親しんでもらおうという狙いもあります。2005年10月から本格的に実施し、土日祝日や年末年始、夏季期間に適用されています。
山形県庄内市 『庄内町農山漁村再生可能エネルギー基本計画』
庄内町では強風をまちづくりに生かすために1980年から風力発電を始め、水田地帯に風車を建設することで、農業と再生可能エネルギーの両立を推進してきました。
そして、農林水産業と調和した再生可能エネルギーの開発により農山漁村の持続可能な発展を目指す「農山漁村再生可能エネルギー法」に基づき、基本計画を策定しました。現在では風力発電は町の電子使用力の約60%を賄っています。また、風力発電は県内の金融機関が融資し、土木や電気工事は町の企業が担っているため、地域経済の活性化に貢献しています。そして風力発電の工事により林道が拡幅され、森林施設や木材運搬などがしやすくなり、人工林の森林整備の推進が期待されています。
最後に
ここまで記事を読んで地球温暖化や地球温暖化による野生動物の現状について少しは理解できたのではないでしょうか。地球温暖化は今や世界規模の問題となっており、このまま人間の生活が豊かになればなるほど解決から遠退くばかりです。自分一人が何か行動したところで何も変わらないと思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、問題を解決するためにまずは現状を知り、関心を持つことが大切です。ここまで記事を読んでくれたあなたはすでに地球温暖化と向き合っています。すでに国や自治体では様々な地球温暖化防止の取り組みが行われています。あなたも今日から私たちが普段何気なく使っている電気によって命の危機に晒されている動物がいるということを忘れずに、小さなことから見直していきませんか。
宜しければSNSでのシェアをお願い致します!