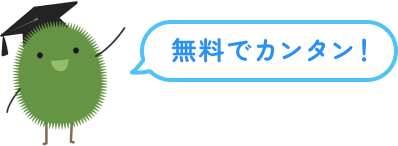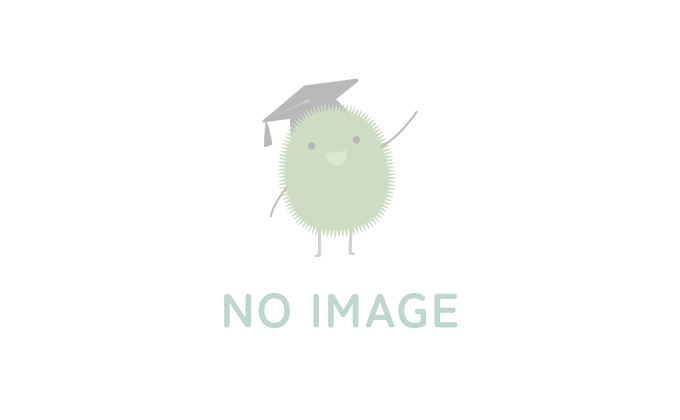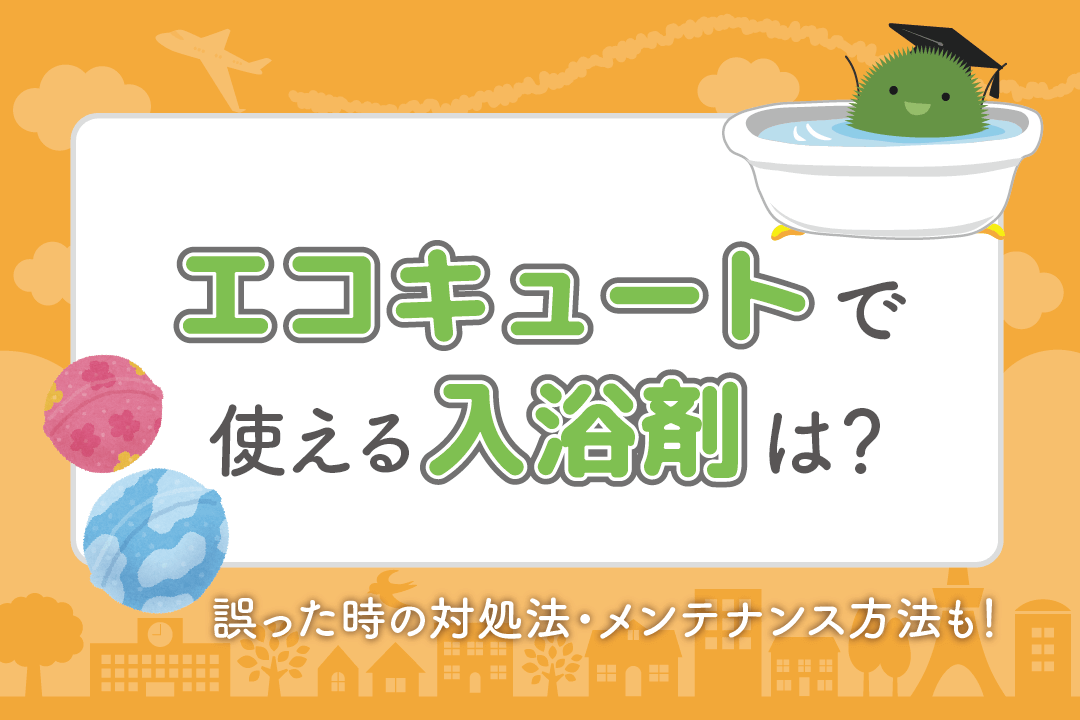環境先進国「スウェーデン」を知る
所属:高崎経済大学
インターン生:T.Aさん

③導入 スウェーデンという国をご存知でしょうか。その国は環境先進国と言われており政府から国民まで、そこに住む大勢の人が環境について考えています。本記事ではそのような環境先進国・スウェーデンの特徴やそこに住む人々の考え、生き方について説明します。
1)理由を知る
そもそも、どうして環境について考えなきゃならないの?
地球上に住む生命に危機が迫っているからです。ニュースを見て、「なんかちょっと、日本おかしいな」と思うことはありませんか?例えば、毎年のように記録する”史上最高〇〇”や異常に短い夏、局地的に襲う激しい雨が思いつくはずです。”数十年に一度”なんて言葉もよく耳にしますね。

このような異常気象は日本だけでなく、世界にもたくさん起こっています。それは気象庁が、世界の週毎の異常気象を公表できるほどたくさんです。気象だけではありません。世界では現在、海洋ゴミ問題や生態系の破壊など、数多くの環境問題を抱えています。
そしてこれらの原因となっているのは、人間の活動です。私たちの行動が地球に悪影響を及ぼし、このような問題を引き起こしているのです。このまま継続していると、人間が住めなくなってしまうかもしれません。
そんなことは起こって欲しくないですよね。人間の住めない地球になることは誰も望まないと思います。だからこそ、私たちの生活を守るため、そして将来誕生する生命のためにも、環境について考え、行動を見直さなければならないのです。
どうしてスウェーデンを選んだの?
環境先進国だから選びました。スウェーデンは20世紀初頭から自然環境の保護に努め、日本よりもずっと早くから環境について考え行動してきました。その結果、2006年には欧州諸国内で最も少ないCO2排出国となっています。
そのような環境先進国スウェーデンですが、そこに住む人々の環境への意識が非常に高いです。さらに、環境について考えてきた長い歴史があります。そのため、スウェーデンに住む方々の知恵や工夫、生き方には私たち日本人も参考にできるものがたくさんあるのではないかと思い、スウェーデンを紹介することに決めました。
2)スウェーデンを知る
地理
スウェーデンとは北欧のスカンジナビア半島に位置し、西ノルウェー東フィンランドに挟まれています。面積は、約45万㎢で日本の1.2倍、人口は約1000万人で日本の0.08倍程度です。日本よりも人口密度が非常に小さいです。
気候は、四季がはっきりしています。これは日本と似ていますね。ただ、夏は日本ほど暑くはならず、冬の寒さは厳しいです。首都のストックホルムでは平均最高気温22℃、最低気温−6℃となっています。
緯度が高い割に暖かい理由は、近くを流れる暖流・メキシコ湾流の影響を受けているからです。もしこの川が流れていなければ、スウェーデンではホッキョクグマが街路を闊歩していると言われています。
国土は約半分が針葉樹林(スギやモミの仲間)に覆われ、多くの広葉樹(桜やカエデの仲間)も散在しているため、木々が色とりどりに変化する秋の紅葉は日本とは違った美しさがあります。首都はストックホルムで南東に位置しています。水資源に恵まれており、「水の都」と言われています。

産業は、南部の平野では、小麦やジャガイモ、テンサイの栽培と酪農が行われています。中部以北では林業が盛んで、漁業はニシン漁などが行われています。公用語はスウェーデン語ですが、英語力が高く英語を第一言語にしない国の中では世界一と言われています。
通貨はスウェーデン・クローナで、日本円に換算すると大体17円ぐらいです。ただ、キャッシュレスが普及しているので、英語力が高いのと併せて旅行がしやすい国であると言えます。
国民
1)几帳面で真面目
スウェーデンに住む方々は、几帳面で真面目な人が多いです。時間を守り、ビジネスでも無駄なお喋り等はしません。またシャイで慎重派な面も持っているため、自ら積極的に関係を持とうという考えの人は稀です。
2)勉強熱心
eurostatによるとスウェーデンの25〜64歳の成人のうち4週間以内に教育もしくは職業訓練を受けたことのある人の割合は30.1%であり、この値はEUでトップです。また、スウェーデンにはスタディーサークルという慣習があります。勉強したい人たちが自主的に参加し、学ぶことを目的としているサークルです。その特徴は以下の通りです。
- サークル数:27万2000
- 合計参加者数:170万人
- 3人いれば結成できる
- 学習協会に登録することで施設・助成金の利用が可能
- 音楽、陶芸、化学、言語などあらゆる科目が対象
このような制度を国が整備していることからも、スウェーデン人が非常に勉強熱心であることが伺えますね。
3)日本とは違った恋愛観
スウェーデンでは、日本のような告白の文化がありません。そのため、彼らと友達以上の関係になった場合には、付き合うという線の境界がはっきりしていないため最初は困惑するかもしれません。正式なデートもなく様々な場所に出かけたり一緒に過ごすことで自然とカップルが出来上がるといった流れです。
4)自然を愛する
長い期間を雪と共に過ごす土地もあり、また大都市であっても近くに自然があることが多いので、夏の緑や自然の恵みに感謝する傾向が強いのでしょう。
5)税金に対する価値観
皆さんは税金に対してどのような印象を持っていますか?様々な意見があるかと思いますが、多くの人が”敵”のような存在に思われていることでしょう。スウェーデン人は違います。彼らは税金を”投資”であると考えています。投資することによっていつか自身が恩恵を受けることを理解しているのです。ここからは政府との信頼関係の厚さを感じさせられますね。
政府
1)充実した社会保障
スウェーデンの社会保障は非常に充実しています。日本でも基本的に何不自由なく暮らせるほど充実していますが、スウェーデンはそれ以上です。スウェーデンの社会保障の特徴として、現役世代向けの社会保障が充実していることが挙げられます。例として、保育や教育、職業訓練、失業保険、育児休暇中の手当が挙げられます。もちろん、年金や医療、介護も充実しており、高齢者のみならず現役世代までもが社会保険・福祉制度の大切さを痛感しています。もちろんそのような制度を成立させるにはお金が必要で、国民の税負担は日本以上です。日本でいう消費税はなんと25%!日本の10%の倍以上ありますね。
2)環境への関心が強い
スウェーデンでは、政府も環境への関心が強いです。例えば、1999年に議会は16政策の目標を採択しました。その中でも特に優先すべきとしているのが、以下の4つです。
- ①気候変動への対策
- ②生物多様性への対策
- ③海洋環境とバルト海の保護
- ④環境効率の良いグリーン・エコノミーへの取り組み
政府は環境保護には厳しい姿勢をとりつつ、ビジネスチャンスであると見ています。環境保護への厳しい姿勢の例として、二酸化炭素税を課しました。1kgあたり13.3円、1トンあたりだと13300円となります。日本では1トンあたり289円ですので、スウェーデンの二酸化炭素税が非常に大きなものであることが分かります。
一方で、環境に優しい動きについては積極的に促進する動きがあり、EVへの税制優遇措置等を行っています。政府は環境教育にも力を入れており、幼稚園から導入されています。この教育で子供たちは、自然と接触しながら生物への知識を深め、自然について学んでいます。
企業
スウェーデンにはサスティナブル先進企業が多いです。「H&M」や「ヌーディージーンズ」などのブランドが代表的で、特にサスティナビリティーの追求に力を入れているように感じられます。
2020、国連が採択した世界をよりよく変えるための17の目標SDGsの現時点での達成率は、対象の166カ国中スウェーデンが1位でした。スウェーデン人は幼い頃から自然の中で過ごし、さらに環境に関する教育を受けています。そのため環境への関心が非常に強いのです。そのような国民で構成された企業であるため、このような結果を残すことには納得できるかと思います。
3)方法を知る
さて、スウェーデンとそこに住む人々の特徴を知っていただいたところで、本題の”方法”について説明させていただきます。ここではスウェーデン人のこんな考えがエコに繋がっているよ、やこんな方法・考えで環境活動を行っているよ、という例を紹介していきます。
1. ラーゴム
「ラーゴム」ってなんだ?って思った方が多いかと思います。「ラーゴム」とは「多すぎず少なすぎず、ちょうど良い」という意味で、スウェーデンでは、生活において何よりも重んじている考え方だそうです。日本には「知足」という言葉があります。辞書によると、自らの分をわきまえて、それ以上のものを求めないこと、という意味です。
これに似ており、「ちょうど良い量が一番いい、ほどほどに止めることが大切」という考え方です。要するに、自分にとってちょうど良いストレスのたまらないバランスを見つける、ということです。この「ラーゴム」がスウェーデンでの暮らしにどのように反映されているのかをいくつかご紹介します。
1)頑張りすぎない
「一日中、頭の中が仕事でいっぱい」という生活は精神的にも肉体的にもよくありません。当然、重要な仕事があるときはその仕事のみを考えるかもしれませんが、それは特別なケースです。そのような生活が続けばストレスが溜まっていくことは明らかです。
スウェーデンには、「フィーカ」があります。日本では似たようなもので10時のおやつ・3時のおやつがありますが、少し違います。好きな時間に家族や友人、職場の仲間など身近な人たちでお喋りをしながら一休みするのが「フィーカ」です。
自宅や職場だけでなく公園のベンチなど、場所や時間に囚われず1日に何度もします。これによりストレスや緊張が解れ、常日頃から穏やかな生活を楽しむことができ、さらに定期的に休憩をとることができるので、仕事中の集中力が増すのです。
2)買いすぎない
身の丈に合わないような衣服や装飾品を身につけたり、必要以上の家具や食料を購入することはしません。そのような暮らしでは、経済的にも過剰な負担がかかる上にいつまで経っても満足できないことを知っているのです。
3)張り切りすぎない
誰かを家に招く時、家を掃除しなきゃ!や何か用意しないと!と思ったりしませんか?スウェーデン人は違います。「ほどほど」で良いのです。張り切って料理はしません。急いで部屋の片付けをすることもありません。招待された側もほどほどで良いため、良い手土産を持っていく必要はないです。そのため、気軽に集まることができるのです。
いかがでしたか。「ラーゴム」は一見エコとは関係のないような考え方に思えますが、これを日常に取り入れることはエコへと繋がります。例えば 2)買いすぎない ではこの行動により国民全体の、モノの購入量が減少します。これにより売る側の人は店の中に置く商品の数を減らすことができ、それに伴い作る量も減らすことができます。つまり、国民が買いすぎないため、企業の人は作りすぎなくて良いのです。そうなると地球上のモノ、例えば木材とかプラスチックとかを使用する量が減るので、エコへと繋がります。このように、「ほどほど」な行動を日常に取り入れることによって、エコへと繋げることができるのです。
2. トラースマッタ
トラースマッタとは、日本語で「裂き織りのマット」と言います。言葉の通り、布を小さく裂いて横糸として織り込みます。これは古くなってしまった布を活用する方法です。それらの布を捨てるのではなく、マットへと形を変えることで再び使えるようにするのです。ここからはスウェーデン人の、物を大切に長く使うという考え方が見えてきますね。
3. 水への意識を高く持つ
スウェーデンでは水の意識が非常に高いです。背景には1960年代に問題となった酸性雨があります。それにより国民は改めて水のありがたさを実感し、水への意識が高まりました。具体的には、シャワーのヘッドを節水型に変える、シャワーを浴びる際には砂時計を置くことが挙げられます。
綺麗な水は無限ではありません。それは日本でも同様です。現在何不自由なく水を利用できていますが、終わりが来る可能性がないとは言い切れません。現在を生きる私たちに何ができるでしょうか。
4. 「質」を大切にする
スウェーデンでは量より質に重きを置いています。そのものは本当に大切なものなのか、長く使えるものなのかと考えます。安くてもすぐに壊れてしまってはまた買うことになります。たくさん買ってたくさん捨てるよりも、質の高い1つのものを長く使う方が長い目で見れば環境にもお財布にも優しいです。
5. 過度に包装されているものは選ばない
スウェーデンでは、過度に包装されているものは選ばれません。日本に来たスウェーデン人は、日本の過度な包装に驚くそうです。というのも、スウェーデンでは量り売りが基本となっているからです。
例えばストックホルムのWaste Lessでは、商品が剥き出しのままや、ナッツなど小さいものは容器に入った形で量り売りしています。買い物客は自分で容器や袋を用意して、買いたいものを移し替えた上でレジに持っていきます。日本ではこのような形態の店は少ないので難しいですが、購入するときは少ない包装のものを意識することが、今の私たちにできることではないでしょうか?
終わりに
以上、本文では理由・スウェーデン・方法について説明をしましたが、いかがだったでしょうか。環境先進国スウェーデンでは、国民だけでなく政府や企業等全てが環境について関心を持っています。そのため、環境に配慮しやすいような環境が十分に整備されており、現時点であまり整備が進んでいない日本で同じようなことをするのは無理!と思うかもしれません。
ただ、忘れてはいけないのは、どんな小さな行いでもそれを積み上げていけば大きな変化を起こすことができる、ということです。塵も積もれば山となる、ということですね。一人一人の行いは小さくても、それが何千、何万となれば大きなものを生み出せるのです。
確かに、日本はスウェーデンとは違います。土地も人口も、国民の考え方や政府の姿も違います。違うことだらけです。そのため、全く同じことをするなんてのは不可能です。しかし、それでも参考にできることは必ずあります。
ラーゴムについて時々思い出してみたり、スウェーデンの人は水を大切にするんだったななど、日常にそういった小さな変化・意識を取り入れることによってゆっくりではありますが、環境に良い影響をもたらすことになります。なので、本記事を読んでスウェーデンに興味をお持ちになったのであれば、彼らの生き方・考え方を参考に、日常に小さな変化を起こしていただければと思います。
宜しければSNSでのシェアをお願い致します!