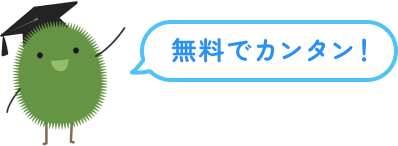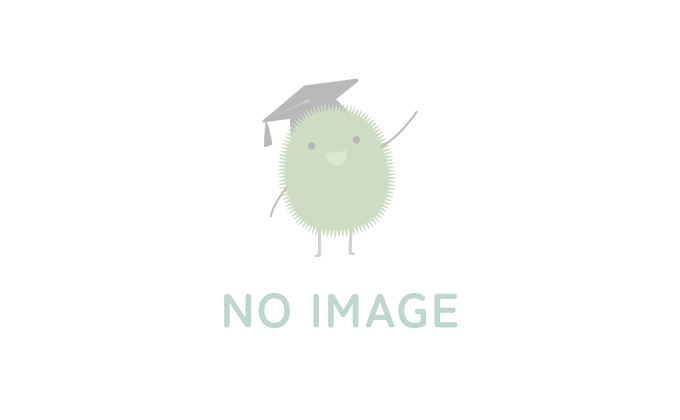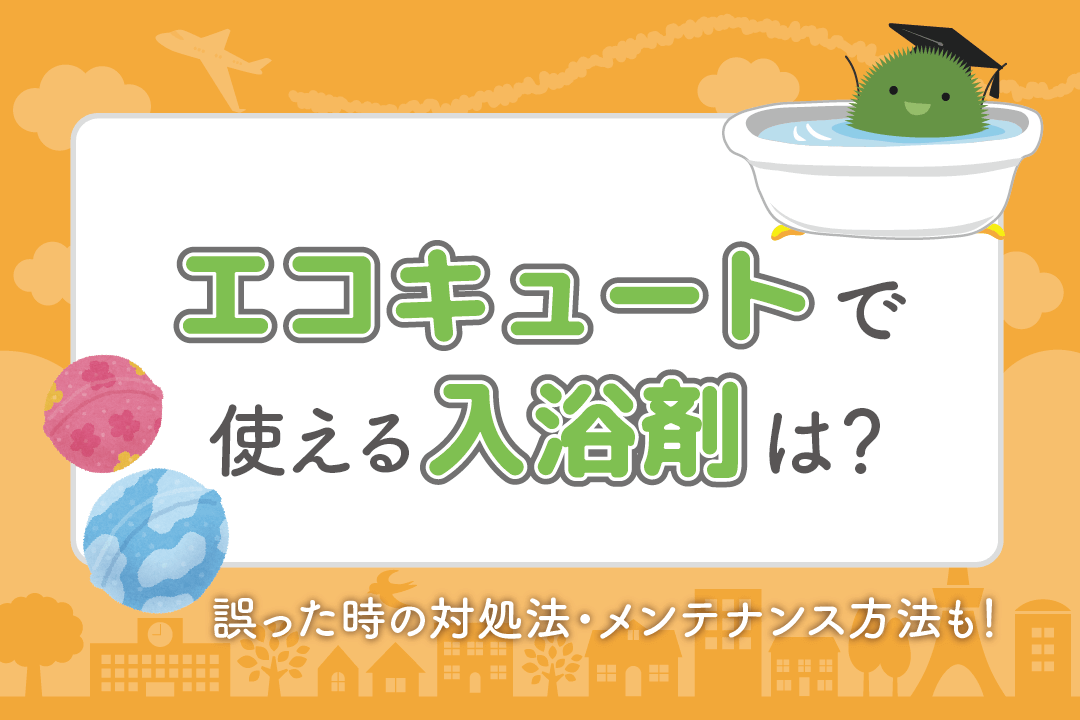ファストファッションが与える環境負荷と「おしゃれ」による環境対策
所属:埼玉大学
インターン生:S.Rさん

人々にとって身近な物の1つに衣服があります。そして、近年のアパレル産業は国際化やファストファッションの普及が進み、現代は人々がより手軽に衣服を購入できおしゃれを楽しめる時代です。しかし、それに伴い、水の大量消費や大量の廃棄が大きな問題となっており、今では「世界2番目の環境汚染産業」とまで言われています。また、新型コロナウイルスの影響により通販の普及も多くなり、梱包資材に関する問題が浮き彫りになってきています。今回はそのアパレル産業の問題点と改善策などについて考えていきます。
アパレル産業の現状
現在のアパレル産業においてファストファッションは業界の売り上げの半数を占めています。また、衣服一枚当たりの単価を考えると生産量はファストファッションブランドが圧倒的に多いという事が分かります。そのため、ファストファッションブランドを基にアパレル産業における環境への負荷を考えていきます。
ファストファッションとは
上記で述べたように、アパレル産業において軸となっていると言っても過言ではないのが「ファストファッション」です。そして、「ファストファッション」は安い、おいしい、早いを売りにしている「ファストフード」から名付けられたと言われており、定義としてはトレンドを取り入れたファッションを安価に売り出しているファッションブランドとされています。
また、大量に生産して世界規模での販売をするブランドが多く、流行に合わせたアイテムを多く販売している事が多いです。ファストファッションにおける有名なブランドとしては「ユニクロ」「H&M」「GU」「無印良品」「ZARA」などがあります。そして、ファストファッションは安さやデザイン性、どこにでもある利便性の良さから私たち大学生のような若い世代から年配の方々まで幅広い世代の方に利用されています。
ファストファッションを基に考える環境問題
アパレル産業において製造から販売また、処分に至るまで様々な環境への問題が存在すると考えられます。そして、アパレル産業の中でも大量生産が著しいファストファッションブランドは、製造工程における環境への影響が一番大きいのもの特徴です。また、最近の新型コロナウイルスの影響で新たに現れた問題点もあります。ここでは、コロナ禍以前から存在する恒常的な問題とコロナ禍以降に顕著になった問題に分けて紹介していきます。
コロナ禍以前からの問題点
コロナ禍以前からの問題点として以下のような事柄が挙げられます。
- 衣類の生産量の急増(2000年度比 約2倍)
- 購入量の増加(2000年度比 約1.7倍)
- 着用期間の短縮(2000年度比 半減)
- 在庫品の焼却処分やポリエステル製品製造によるCO₂排出(全CO₂排出量の10%)
- 衣類の洗濯による海洋へのマイクロファイバー流出(年間50万トン)/li>
- 綿花栽培における農薬の使用と流出
上記の事柄において①~③は特にファストファッションの影響が大きいと考えられます。まず、①はファストファッションにおける大量生産によって起こった問題であると言えます。次に、②は大量生産に伴い、価格が安価になり消費者が手軽に購入できるようになったことで起こった問題であると言えます。そして、③はファストファッションブランドが他の品質を売りにしているブランドに比べて品質が劣ってしまうことや流行の変化が早くなったことが関係していると考えられます。
そして何より、購入量の増加と着用期間の短縮が並行して起こっていることから一点の品の良い衣服をメンテナンスしながら長年着用するのではなく、安価な衣服の購入と廃棄を短いスパンで行う様な着用が主流になっていることが読み取れます。これはファストファッションが広まる以前とは真逆の形態になったと言えます。 そして、①~③の問題の結果として④~⑥のような大きな問題に繋がっていると考えられます。
コロナ禍以降の問題点
コロナ禍以降に取り上げられるようになった問題として以下のような事柄があります。
- 衣類の購入量の低下
- 倒産企業増加による在庫処分の急増
- 配送の急増による梱包資材の増加(コロナ禍前比 約2倍)
上記の事柄において①,②はコロナ禍によって外出の機会が減った事に伴い消費者の購買意欲が減少したことが主な原因だと考えられます。しかし、その一方で購買意欲のある人たちは、店舗に赴けないため通販を用いて商品を購入するようになりました。
この通販先の主な例としては「ZOZOTOWN」「amazon」などが挙げられます。そしてこの通販の利用増加に伴い③にあるように梱包資材の増加が倍増してしまい問題となっています。また、衣類おける梱包に関して配送時しわなどが出来ないように配慮する必要があり、他の配送物に比べ大きな梱包を用いる必要があるのも問題言えます。
アパレル産業による生態系への影響
アパレル産業によって引き起こされる様々な環境問題がどれだけ大きく、どれだけ深刻なのかが次第に浮き彫りになってきました。そして、その環境問題は私たちや生態系全体に直接影響を及ぼしてきます。その具体例を紹介していきます。
マイクロファイバーの流出
衣類の洗濯に伴い大量のマイクロファイバーが海洋に流出しています。そして、現在もマイクロファイバー自体は無害な物質として扱われています。しかし、マイクロファイバーの表面には最大100万倍の有害物質を吸着させることが出来ると言われています。
そのため、マイクロファイバー摂取に伴う弊害の方が問題視されています。その主な問題として、小さい魚がマイクロファイバーを取り込めるため生物濃縮が起こりやすいという点が挙げられます。この生物濃縮とは、マイクロファイバーを取り込んだ魚等を食べる捕食者Aにさらなるマイクロファイバーが蓄積され、次はその捕食者A等を食べる捕食者Bにさらなるマイクロファイバーが蓄積されていってしまうと言うものです。
その結果として食物連鎖的に生態ピラミッド上位にいくに連れて有害物質が濃縮されていきます。そのため、海洋に生息する魚を食べている人間にも連鎖的に有害物質の生物濃縮が起こっていることが分かります。
また、このマイクロファイバーは魚等の体内のみならず、水道水やミネラルウォーター、海塩におけるまで水に関する様々な物から発見されているためマイクロファイバーの削減が非常に重要になってくると考えられます。
綿花栽培に伴う農薬使用のリスク
綿花栽培は他の栽培に比べ大量の農薬を使用します。また、綿花の世界での栽培面積はわずか2.5%です。しかし、農薬に関しては全世界使用量を基準として殺虫剤は25%、防菌剤、除菌剤は10%もの量を使用しています。その結果、1キロの綿花に対し約5キロの農薬が散布されています。この農薬利用率の数値から分かるように綿花栽培の従事者は発がんやその他病気にかかりうる危険性と隣り合わせで栽培を行っていることが分かります。
また、綿花栽培による環境破壊が起きた地域としてアラル海があります。この地域は、綿花開発以前は漁業の盛んな地域でした。しかし、1940年代に綿花栽培が開始され、アラル海に流れ込む河川の水を大量に使用してしまいます。そして、その弊害としてアラル海に流れ込む水量が激減してしまい、1970年代には年間約60cmもの水面低下が起こる事になります。
その結果、街の漁業は継続不可能になるとともに、干上がったアラル海から塩分や化学物質を含む砂嵐が起こるようになり周辺住人の8割もの人が腎臓・呼吸器に疾患を持つようになってしまいます。このアラル海の問題は、人体への影響のみならず産業にまで影響を及ぼす危険性が示されている事例の1つと言えます。
衣類の処分問題
現在、アパレル産業からは毎年9200万トン(約350億着)もの繊維ゴミが廃棄されており、2030年には約1億5000万トン(約530億着)まで増加すると予想されています。これは現在のアパレル産業のゴミは1人当たり175キロの繊維ゴミが出ていることになります。日本における衣服の年間購入枚数は平均50着とされており、一枚当たりの重さが平均0.5キロのため、これを考慮して計算すると年間の購入量は25キロ程度になり、約150キロの衣服が廃棄されていることが分かります。
そして何より、一番の問題は衣類処分の約9割が焼却によって行われていることです。この焼却により化学繊維などの有害物質はもちろん大量のCO₂が排出されることになってしまいます。結果として、アパレル産業によるCO₂排出量は全体の約9%も占めてしまっています。
この大量のCO₂排出によって温暖化問題をはじめとする様々な環境問題が引き起こされてしまっています。この、「温暖化」と言う単語を聞いて大きな被害が及んでいないように感じる方も多いと思います。しかし、近年多発している大型台風や大規模森林火災など温暖化による影響で自然災害の規模が大きくなってきているのが現状です。日本国内においても集中的豪雨による洪水や大気汚染などが近年になって急増しているのが現状です。これらのことから、CO₂の排出も人々や生態系に大きな影響を及ぼす問題の1つであると言えます。
今後アパレル産業はどのような変化をしていくべきか
アパレル産業と環境問題は深く関連していることが分かりました。ここからは、アパレル産業における問題を踏まえ環境への負荷を減らすために今後のアパレル産業はどう変化していくべきか、また私たち消費者はどのような取り組みが出来るのかの2点について考えていきたいと思います。
アパレル産業による環境対策
アパレル産業による環境対策は衣類の製作工程における水の利用削減や生産量の見直し、また処分の手段改善など各工程においていくつも対策をあげられるのが特徴です。ここでは、その対策についてより詳しく説明していきます。
製造工程における工夫
アパレル産業の環境影響を考えていく上で一番の肝になるのがこの製造工程です。製造工程を改善すると消費から処分に至るすべての工程の環境負荷の軽減が期待できます。ここでは、今後の製造工程において重要な工夫例をいくつか紹介します。
①生産量の見直し
現在のアパレル産業はより安い製品を提供するために、大量生産が基本になっています。しかし、その結果処分量が増えてしまっています。この問題を防ぐために、処分量の多い企業などは生産量の見直しが必要です。そして生産量を見直すためには消費者の需要の分析やトレンドの傾向分析などアパレル産業の専門的分析が必要になると言えます。
②品質の改善
現在のアパレル産業の傾向としてファストファッションが人気であるため、低品質のものが普及することが多くなり衣類の消耗が激しくなってしまっています。そしてそれに伴い、着用期間の減少や海洋へのマイクロファイバー流出など様々な問題が起こっています。
このような問題を防ぎ改善するためにも高品質の製品を製造することは重要です。例として、アウトドアブランドとして有名な「パタゴニア」では洗濯時の繊維流出が4割ほど押さえられるように合成繊維の改善や、製造時の織り方の工夫を施しています。このような合成繊維の改善は製品の耐久性が上がり着用期間が伸びるだけでなく、洗濯時の繊維流出を大幅に削減できるため品質改善は環境対策として優れた手段だと言えます。
しかし、耐久性が優れた製品が多くなることは後々に衣服の購入頻度が減少することに繋がる可能性があります。そのため、消費者の購入頻度の傾向をより分析し①にある生産量を関連させてより深く考えることが重要です。
③エシカルファッションの導入
アパレル産業において近年特に注目されているのがエシカルファッションです。エシカルファッションの直訳としては「倫理的・道徳的なファッション」という意味です。簡単に言うと、人や地球環境に配慮した衣類・小物を選び、それらのアイテムでコーディネートし自己表現することです。そのためエシカルファッションの導入は環境の負担が抑えられると言えます。
このエシカルファッションにおける具体的な例として、農薬の少ないオーガニックコットンの使用やサステナブルマテリアルの使用、ローカルメイドなどが挙げられます。今回は、この3つに注目して少し詳しく説明します。
オーガニックコットン
オーガニックコットンとは普通の製造工程であれば大量に用いられる農薬や肥料をなるべく最小限に抑え、厳格な基準のもと生産されたコットンのことを言います。そのため、普通のコットンに比べ費用は約2倍になってしまいます。しかし、綿花栽培に従事する農家の発がんや病気のリスクはぐんと下がる他、土地への環境負荷も軽減されるためオーガニックコットンの購入は環境に優しい選択であると言えます。
サステナブルマテリアル
サステナブルマテリアルとは環境負荷がより低い素材を活用することを言います。特に生地を例として挙げると天然素材、エコな化学繊維、リサイクル繊維などがあります。この中でリサイクル繊維に関して例を挙げると「ナイキ」や「アディダス」などをはじめとする世界的に有名なスポーツブランドが力を入れています。特にアディダスは海洋にあるマイクロプラスチック、マイクロファイバーのリサイクルに力を入れています。そして、最近ではマイクロファイバーなどを含むリサイクル繊維のみで製造したランニングシューズなどが開発され、世界的にも注目を集めています。
ローカルメイド
ローカルメイドとは地域に根ざしたものづくりで地域産業/産地を活性化させ、雇用の創出、技術の伝承と向上を目指すことで、日本を例に取ると「MADE IN JAPAN」のことです。より砕いて言うと、衣服における地産地消のような形態のことを指します。日本では「TOKO BASE」や「Factelier」などの企業が挙げられます。そして、このローカルメイドにおける良い点としては優れた繊維や伝統技術などが取り入れられているため商品の消耗が抑えられる点や国内だけで生産供給ができるため輸送などにおける燃料消費が大きく抑えられる点が挙げられます。そのため、ローカルメイドはファストファッションなどの大量生産に比べ環境負荷が抑えられると言えます。
処分行程における工夫
現在のアパレル産業におけるCO₂排出の主な原因は処理工程の焼却処分にあります。そのため、衣類の処理工程の改善はCO₂排出の緩和にも繋がると言えます。ここでは、処理工程において焼却処分を減らすためのいくつかの工夫を紹介します。
①限定セールなどでの売り切り
現在のファッション産業はトレンドのサイクルが速いため、シーズンを持ち越しての販売を好まない傾向にあります。その結果として処理の手間や値段が手頃な焼却処分が多くなってしまっています。これを防ぐ為に通常のセールの他、今まで購入歴のある見込み客や従業員を対象として通常セールよりさらに安くした限定セールなどを行うと焼却処分に持ち越す衣類の量は削減できるのではないかと考えられます。
②リメイク商品など限定商品の開発
処分商品の削減方法としてリメイクが挙げられます。リメイクの利点として、リサイクルのように素材に手を加える科学技術が不要です。そのため、リサイクルに比べ製造工程の環境負荷も軽減することができます。しかし、費用の面からリサイクルをする企業は少なく世界的ブランドである「ルイヴィトン」や「シャネル」なども焼却処分しているのが現状です。しかし、特にこのような世界的ブランドであれば他ブランドに在庫を提供し、リメイク商品を開発して付加価値を持たせることができると考えられます。また、その結果としていずれのブランドも処分すべき商品が減り焼却処分の削減つながると考えられます。
消費者による環境対策
ここまではアパレル産業の環境対策例を紹介しました。次は、私たち消費者はどのような対策が出来るのかをいくつか例を挙げて紹介していきます。
私たちに出来る環境対策例
①環境に配慮した衣服の購入
私たち消費者ができる一番簡単な環境対策はやはり購入前に商品自体の環境影響を考慮することです。実際、最近の衣類にはタグにリサイクル繊維で出来ていることや、環境に配慮して作られていることなどが書かれていることが多いです。どこまで環境配慮をしているのかを一から知ることはできませんが、何も配慮していない商品を買うよりも確実に環境負荷を軽減できます。
他にも好きなブランドなどがある方の場合、サイトを調べ環境への対策などを調べることができると思います。そして、環境への配慮が確認できれば、それ以降、意図せずとも環境を配慮しながら商品を購入することができます。
②衣服のメンテナンス
私たち消費者は日々、洗濯やクリーニングなどをして衣服をメンテナンスする必要があります。しかし、どんなに良い品質のものでも表示通りに洗濯をしなかったりすると繊維が劣化してしまいます。そして、結果として衣類の消耗が早くなる他、マイクロファイバーの問題などに直結してしまいます。そのため、日々の適切なメンテナンスも環境対策につながると言えます。
③フリマ、古着屋の活用
最近の衣服はトレンドの移り変わりが速いため、問題なく着用できる品でも持ち主にとって不要になり捨ててしまう場合があります。しかし、それでは環境への負荷が増してしまう一方です。そのため、衣服を捨てる前にフリマで安い価格で販売することや要らない服を古着屋などに持っていくことが重要だと言えます。また、最近の古着屋では売りに出せない商品でも処分せず海外の貧困地域に届けている店も多くなっています。このようなことから、捨てる前の一手間が環境への配慮のみならず様々な面でプラスに働くと言えます。
まとめ
今回は私たちのすぐ身近にある衣服と環境問題の関係性について取り上げました。今回の記事を通して皆さんが普段何気なく楽しんでいるおしゃれの裏には世界規模での環境問題が潜んでいることが分かったと思います。すべての状況を一気に改善することは出来ません。しかし、皆さん一人一人の意識の変化で徐々に問題を改善することが出来ます。
簡単な例として、衣服選ぶ際、デザイン性や快適性の他に「環境への配慮」という項目を追加する事が挙げられます。この簡単な意識一つだけでも環境配慮に向けた大きな一歩になると言えます。そして、結果として環境への配慮をしながらおしゃれを楽しむ人が増えていくことが出来ればより良い“おしゃれ×環境”の構図が出来ると思います。
宜しければSNSでのシェアをお願い致します!