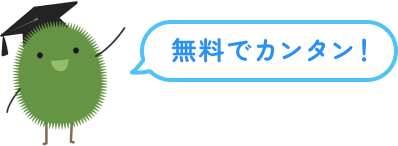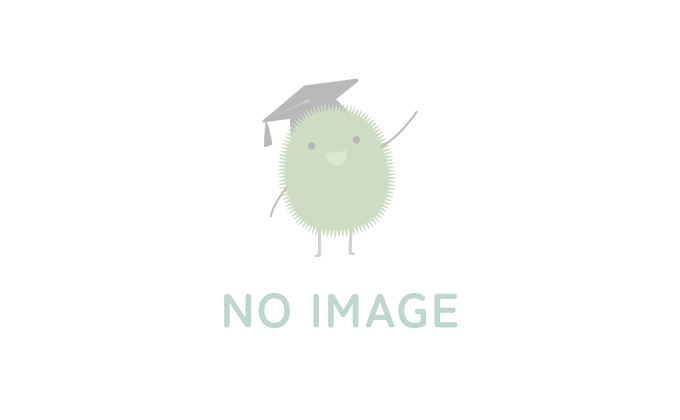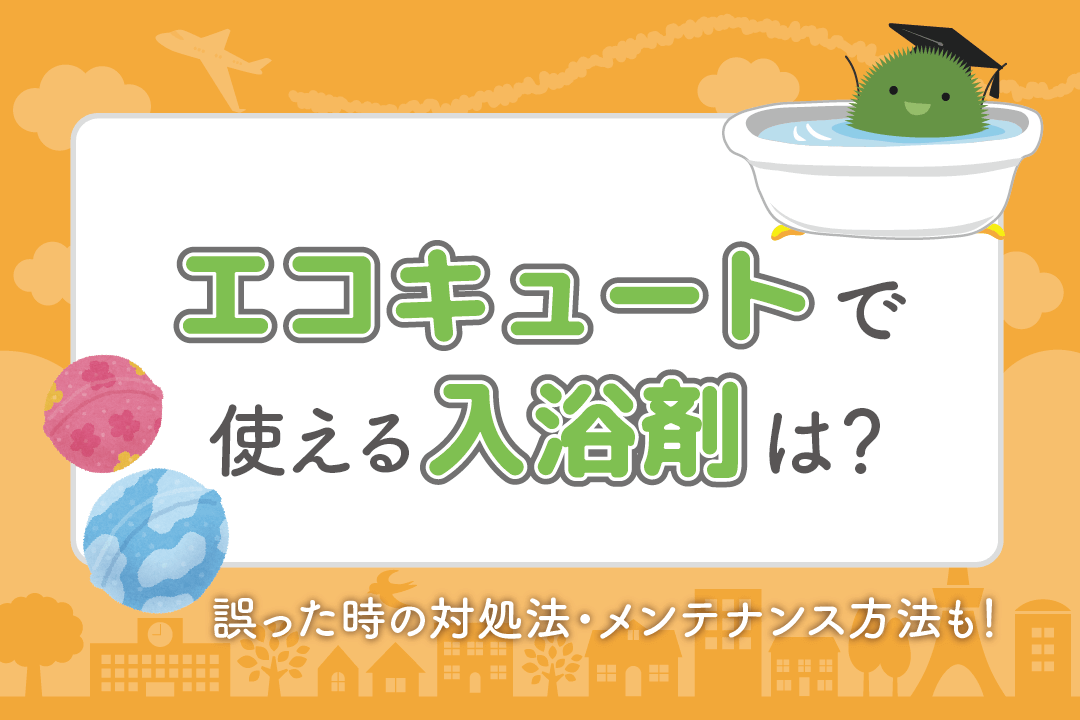マングローブの可能性
所属:法政大学
インターン生:Y.Mさん

生態系サービスという言葉をご存知でしょうか。この生き物たちの恩恵は私たちの生活とは切っても切れないものですが、あまり聞きなれない言葉かもしれません。WWFのレポートによると、過去30年間の間に世界の自然の豊かさは3割失われてしまったそうです。今回は私が鹿児島県、奄美大島とタイで見たマングローブを例に挙げて生態系サービスの重要性についてみていきたいと思います。
マングローブとは
そもそもマングローブという水辺に生える植物種があると思っている方も少なくないのではと思います。実は汽水域に生息する植物のことをまとめてマングローブと呼んでいて、マングローブという名の植物があるわけではありません。
マングローブに分類される植物は世界に110種類以上あります。マングローブは123カ国の国と地域に分布しており、総面積は152360平方キロメートルで世界の熱帯雨林の1%、世界の森林の総面積の0.4%を占めています。数字だけみると決して多くは見えませんが、マングローブ域ならではの特徴を生かして、他の生き物に多くの恩恵を与えています。
根
酸素を取り込む筍根や膝根、泥質の土でもしっかり体を支える支柱根、板根、木が倒れてしまっても成長できるようにするための不定根など様々な種類の根を持っています。
葉
汽水域にいるマングローブ植物は、体内が塩でいっぱいになり死んでしまうことを防ぐため、葉は黄色になりすぐに取れてしまいます。
日本のマングローブ
マングローブと聞くとなんとなく南の国のイメージがありますが、日本でもマングローブを見ることができます。例えば、沖縄や鹿児島県の種子島、自然分布のマングローブの北限である奄美大島も知られています。意外と知られていないところだと、静岡県の伊豆半島の先端の青野川の河口付近にコンクリート堤で囲まれたメヒルギの群落があります。
しかし、これらは昭和34年に人の手によって植えられたものであることから、正式なマングローブの北限とはされていません。当時、青野川の河口にアマボウという塩生植物が生えていたことから、有用植物園園長であった竹下氏はマングローブも育つのではないかと考えました。
そして、種子島のメヒルギの胎生種子を植え、一度は失敗したものの昭和35年に活着に成功しました。一時は600株ほどにまで増えましたが、その後の護岸工事によりかなりの部分が切り取られてしまいました。青野川のマングローブの風景は人の手によって作られたものであり、東南アジアや鹿児島、沖縄のものと比べると少し寂しくも見えますが、貴重なマングローブの景観が自分の出身地にあるということを誇りに思います。
生態系サービスとは
生物多様性が人類に提供してくれる物質的、また非物質的恩恵のことをいいます。国連のミレニアム生態系評価は、主に4つのサービスに分類しています。
- ① 供給:食べ物や水、木材、繊維、燃料、薬品、工芸品の材料
- ② 調整:水を蓄え浄化、温度を下げる、洪水を防ぐ、廃棄物を分解
- ③ 文化的:レクリエーション、信仰の対象、教育の場、目を楽しませてくれる
- ④ 基盤:①~③のサービスの基盤となるもの→光合成によって酸素をつくる、水を循環させる、森で降った雨を葉や土壌に一度蓄えてから鉄分などのミネラルをたっぷり含んだ水にして川から海に流す、栄養塩を循環させる
それぞれに当てはまるマングローブの生態系サービスは以下の通りです。
①供給
薬や家具、食材等の原料として利用
根は薬、虫よけ、熱冷まし、皮膚治療など、木は家具、船、橋などの材料、実はカレーやおかゆに入れたり油として使われたりしています。
生物多様性の保全
マングローブ植物自体の花の蜜や果実を求めて、昆虫や鳥、サルまでもが集まってきます。マングローブの複雑な形の根は海生生物の住処となります。またマングローブの枯木や一年中少しずつ落とす落ち葉を求めて微生物や昆虫、貝類、エビ、カニ類などの分解者がやってきます。
それを食べて魚が育ち、その死骸やフンがまた植物の栄養となります。マングローブが生息する汽水域は潮の満ち引きがあるので、海の魚、川の魚どちらも住むことができます。干潮時には干潟ができそこにいる動物を求めて他の消費者がやってきて、満潮時にはマングローブ林のプランクトンを求めて魚が集まってきます。そして、その魚を求めて鳥がやってきます。この豊かな海岸の生態系を保っているマングローブは、海のゆりかごと呼ばれているほどです。
マングローブ林は生き物の住処であり餌場であり、陸の生態系も海の生態系もどちらも育まれています。このように、様々な種類の生き物が生きる環境が整っており、豊かな生態系と動物相が育まれているマングローブは、貴重な生態系サービスを提供してくれる場のひとつとなっています。豊かな水産資源を生み出すマングローブ域では漁業が盛んに行われ、地元の漁師はマングローブの豊かな生態系サービスの恩恵を受けているのです。
②調整
護岸林、防災林としての活用
近年地球温暖化の影響で海面が上昇していますが、それによる海岸浸食から海岸線を守ってくれるのがマングローブです。2004年に発生したマグニチュード9.1のスマトラ島沖地震では、巨大な津波が起き死傷者は30万人以上にものぼりました。
これだけの破壊力のある大津波でも、マングローブ林があったところではそのスピードが抑えられ、漂流物の通過を防止し、津波被害を軽減させることができたといいます。これは、マングローブの柔軟性と独特な根で地面をつかみ簡単には倒れないよう固定されていることによるものです。日本でも慶長の役の際に、薩摩藩がメヒルギを琉球から持ち帰り、護岸林として奄美大島や種子島に防災用に植栽しています。
水の浄化
マングローブ生息域付近で魚の加工工場から排水が垂れ流しにされてしまうことがあるが、マングローブの水質を浄化する効果により助けられることがあります。
③文化的
エコツアーの場
エコツーリズムの考え方に基づいた、マングローブ林でのエコツアーも実施されています。このようなツアーを通して、観光客や地域住民たち参加者にマングローブをより身近に感じてもらい、マングローブ保全の重要性を理解してもらうことをねらいとしています。
マレーシアや沖縄の石垣島、宮古島でこのマングローブツアーが行われています。また、ナショナルジオグラフィックとローソントラベルがマングローブ散策の行程を組み込んだツアーを共同開発するなどしています。私も以前奄美大島に訪れた際にガイドが付いたマングローブカヌーツアーに参加し、マングローブについて学ぶとともに、自然に触れることができました。これはその地域の観光の目玉ともなっており、地元経済の活性化にも一役買っています。
④基盤
高い炭素固定機能
マングローブを含む沿岸生態系は、堆積物の中に炭素を数百年、数千年という長いスパンでとどめておくことができます。これにより、温室効果ガスの中の多くの割合を占める二酸化炭素を閉じ込め吸収し、温暖化から地球を守ることができるのです。
生物多様性と生態系サービス
生物多様性が豊かなほど生態系サービスも大きくなるという場合が多くみられます。遺伝的多様性が保全されることにより、将来の医薬品開発や品種改良につながる可能性が確保される農地周辺の昆虫などの種の多様性が高いほど、花粉媒介や病虫害の抑制といった調整サービスが向上する生態系サービスの持続可能な利用には生物多様性の保全が不可欠です。
数字で見る生態系サービス
2010年10月、名古屋で開催された第10回生物多様性条約締結国会議において、国連環境計画は生態系と生物多様性の経済学の最終報告書を公表しました。その中では動植物や森林の保護などの生態系保全に年450億ドル、日本円にして約3兆6千億円を投じれば長期的に見れば水産資源の増加や温暖化防止効果などで年5兆ドル、日本円にして約400兆円の経済価値を生み出せるとし、保全を一切しないと最大で年4兆5千億ドルもの損失が出る可能性があるとしました。
マングローブに関する例を見ると、ベトナムでは堤防の維持に730万ドルをかけましたが、津波被害の軽減効果が期待できるマングローブを保全する方法を選べば、約1万2千ヘクタールに対して110万ドルで済むそうです。費用対効果は堤防を造るより、マングローブの保全が上回るということになります。つまり、それだけマングローブのもたらす生態系サービス、ここでは調整サービスは大きいといえます。
マングローブの破壊~エビとマングローブ~
多くのマングローブの恩恵がありながらも、マングローブは人間の手によって破壊され特にアジアで減少を続けています。2010年までの20年間で全世界のマングローブ林の35%が失われてしまいました。私が夏に訪れたタイ、ソンクラ―では1975年~1996年の間に89.4%のマングローブが約20年間に失われてしまったそうです。
破壊の要因としては、マングローブ炭の商品化拡大、エビ養殖池、スズ採掘場、塩田、稲作、オイルパームのプランテーションへの転換や防波堤が作られたこと、また都市化による道路の設置、工場の建設、油や化学物質の流出事故などが挙げられます。
特にエビ養殖は深刻な問題です。1970年代から2000年代初頭に世界八カ国で行った調査では、マングローブが伐採された土地の54%が魚やエビの水産養殖の池として利用されており、2000年から2012にかけては30%が水産養殖用に置き換えられています。シンガポールでは在来種のマングローブ林の90%がすでに失われてしまいました。
タイ、ソンクラ―の海岸線ではエビ養殖池が一面に並んでいたのが印象的でした。1992年は養殖によるエビの生産量は世界のエビ類生産量全体の30%ほどでしたが、2012年には生産量の過半数を超えて56%に増加しました。1990年代はじめの日本におけるエビ消費量は年に約33万トン、そのうち日本国内で賄われているのは年間約4.7万トンなので、80%以上を輸入に頼っていることになります。
この量を一人当たりの消費量に換算すると、2.6キログラムとなり、日本では世界第二位のアメリカの1.2キログラムの2倍以上もエビを食べているのでエビ大量消費国といえます。たしかに、冷凍食品やカップラーメン、エビフライやてんぷら、寿司…私たち日本人がエビを食べる機会は多いです。
1998年には全世界で年間約250万トンのエビが水揚げされ、その生産量のうち約82%は主に東南アジアの発展途上国からのもので、そのほとんどはマングローブの分布地です。日本人はエビを食べることによって、マングローブ林をも食べているというような表現がありますが、大げさにいえば、エビを食べることによって生態系を破壊しているともいえるのではないでしょうか。
私たち日本人が大量消費しているエビが、マングローブの破壊、とくに東南アジアのマングローブ林の消失に直接結びついているということはあまり知られていません。このようにマングローブが破壊され続けてしまえば、その自然の恵みを失ってしまうことになります。
日本企業とマングローブ保全
現在ではこれまでに述べたようなマングローブの破壊を食い止め、後世に残していこうという保全活動が広がっています。ユネスコや政府、自然保護団体による働きかけでマングローブや湿地の重要性が認識されるようになり、1980年末ごろからはマングローブ林の伐採禁止や土地の他の目的での転換禁止のような政策が打ち出されるようになりました。
また、国立公園や自然保護区に指定し保護するという保全の方法がとられたり、各国の政府の行政機関やNGOが進んで取り組んでいる植林支援に触発され、その活動は多くの企業に広がっています。
東京海上日動
創業120周年記念事業の一環として、1999年から5年間で東南アジア5ヶ国において3444ヘクタールのマングローブ植林を実施し、2004年からは第2期プロジェクトとして東南アジア5ヶ国に南太平洋諸国のフィジーを加えた6ヶ国で、5年間に2000ヘクタールのマングローブ植林を実施しました。
そして2009年からも、第3期プロジェクトが始まっています。タイでは2000年からラノーン県及びチュンポン県で実施し、第1期、第2期あわせて900ヘクタールの植林を実施しました。そして、東京海上日動のコマーシャルにもラノーン県で植えられたマングローブ林が一部に使われており、マングローブ植林を世間に伝える一つのツールとなりました。
あいや
2001年から2年ごとにフィリピン、タイ、インドネシア、マレーシア、ベトナムで植林活動を実施しています。社員の社員旅行や社員研修をかねての社会貢献と人材育成のプログラムで、社員のほぼ全員が参加しています。
全日本空輸
2005年から2007年にかけてタイ北部やプーケット、チャイナット県で植林支援を行ってきました。2005年にはプーケットで、2006年はチェンマイで、そして2007年にはタイ中部チャイナット県での植林が行われました。これは「私の青空」という全日本空輸の森づくり活動の一環で取り組まれていたものです。
イナ・デザインコンサルティングシステムズ
多種多様なイベントやプロジェクトなどを企画しており、企画されたイベントの入場者の入場料の一部を、2008年から植林支援へあてています。独自の植林地を持ち、5ヘクタールのマングローブ再生プロジェクトを実施しました。参加者を募ってツアーを実施するというものではなく、身近なところから日本の若者が環境活動へ目を向けられるきっかけ作りとして、新しいアイデアの提案をすることに積極的に取り組んでいます。
ダンロップ
2009年にタイのラノーンの街の中にあるマングローブの森、コミュニティフォレストを再生するプロジェクト、「チームエナセーブ」として200ヘクタールのマングローブ植林支援プロジェクトを行いました。ラノーン市内の川はゴミや汚水で汚れてしまっているが、その汚れた川を浄化しているのがまさに街中にあるマングローブの森です。
NEC
いくつかの大学、国立環境研究所と共に自社のスーパーコンピューターを用いて、マングローブ林による減災効果をシミュレーションするシステムの研究開発を開始しました。このように、様々なフィールドの企業が異なるアプローチでのマングローブ植林、再生への支援を行っています。
保全の問題
先に述べたマングローブの植林やエコツアーは、保全に有効ではありますが問題点も抱えています。一部のボランティア団体が植林後の管理を怠り、マングローブを枯らしてしまう植えるマングローブがそこにもともとない種で、そもそもマングローブが生えていない場所にマングローブを植林してしまうエコツアーの普及による人、船の流入などです。
外から来た団体が中途半端な支援をしてしまうと、マングローブ域の住民にも迷惑なうえに環境保護のイメージダウンにもつながりかねないといえます。また、マングローブ域の自然を乱したり破壊したりして、マングローブの生態系を回復させるどころか逆に乏しくさせてしまうこともあります。
ベトナムのマングローブ林保全
ベトナム、カンザーのマングローブ林はホーチミンから車で約2時間、サイゴン川の下流域の広大な湿地帯にあり、約7万5000ヘクタールに及ぶ規模は東南アジア最大級と言われています。ベトナム戦争の時、このあたりにはベトコンの拠点がありました。
そのためアメリカ軍は1970年代に400万リットルという大量の枯葉剤散布を行い、当時のマングローブの38%にあたる約4万ヘクタールがそのときに失われてしまいました。しかしその後、マングローブ林の復活を望む地元民やベトナム政府、NGOなどが協力して植林を行い、現在のように約30種類のマングローブからなる雄大な森が蘇りました。
今後の課題
マングローブ生態系においては、それを取り巻くアクターの知識不足の解消と管理や観光のルール作りの徹底が求められると考えます。それにより正しい知識が広がれば、正しい保全も広がっていくはずです。 また日本では多様な生物相を支える里地・里山を守っていくことが課題です。
近年、里山地域では人口流出や住民の高齢化が進み、その資源や環境を管理する人が減っています。今後はまず、「生態系サービス」という言葉がより一般化されていくことが必要になると思います。現在は環境というと「温暖化」という言葉の方がメジャーでそちらに目が向けられがちです。
でも、ここで私たちの生活の中のあたりまえになっている生態系サービスというものに目を向けてみるのはどうでしょうか。宮城のふゆみずたんぼ農家の方が何万匹という雁の群れが飛び立つ迫力を肌で感じたとき、人間が環境を保全・保護するというのはおこがましいと感じたそうです。どう自然と寄り添って生きていくか。これを考えてみる必要があるのかもしれません。
宜しければSNSでのシェアをお願い致します!