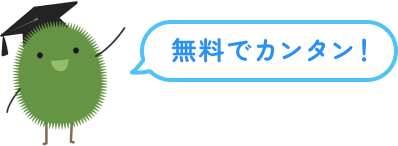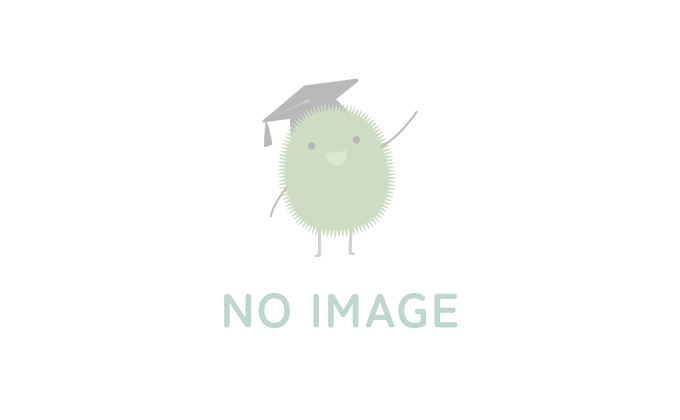原発事故後の政府と企業・市民の節電対策について
所属:--
インターン生:--

2011年3月11日東北地方でマグネチュード9の大地震が発生し福島第一・二原発が地震・津波の被害により原子炉に保管されていた放射能が周囲20キロ圏内の人たちが避難しました。

RAULのインターンシップに参加いただいた--の--が執筆してくれた記事だモ!内容がご参考になりましたら、ぜひともイイネやシェアしてほしいだモ!
2011年3月11日東北地方でマグネチュード9の大地震が発生し多くの人が津波によって亡くなってしまったがその時同じくして福島第一・二原発が地震・津波の被害により原子炉に保管されていた放射能が周囲20キロ圏内の人たちが避難しました。
当時私は高校一年生で突然襲ってきたあの地震をよく覚えています。特に私が記憶しているのは全ての原発が運転中止となりその後政府が夏の電力の需要を賄うために「計画停電」を計画し一般市民・企業も「節電」という電気の消費を減らしていく活動を行っていたことがテレビなどで何度も放送していました。しかし原発が再稼働するまで特に大きな停電・電力不足で騒がれた記憶はなく本当に必要であったのかと私は疑問に感じました。そのことについて「計画停電」と「節電」の二つに分けて論じていきます。
まず「節電」について
一般の人でも行える節電方法としてエアコンの温度を一度上昇させることにより一割の節電に電球をLEDに変更したり待機電力を減らしていくことで無駄な電力消費を減らしていく方法があります。企業では「ピークシフト」という電力消費がピークに達する時間帯の電力使用を抑えるために平日夜間から早朝または土日の休みの日に働くことそのような製品を開発していくことがありました。
次に「計画停電」について
その時の「計画停電」は主に東京・東北地方を中心に時間・地域ごとに行われていきました。しかし実際は火力発電の電力供給が十分に稼働していたり「計画停電」を行う地域に連絡が不十分であったり浦安市では液状化による被害の復旧作業時に停電が実行されてしまい、さらに停電を行う地域に発電所が存在していたことが後々になってわかるなど連絡網が未完成な状態でありましたが節電対策としてはほぼ問題ありませんでした。
以上のように今回の原発事故による政府と企業・一般市民の節電対策としては問題なかったですが一番の問題点はむしろ成果と実態をうまく報道できていないことであると思います。計画停電でも場所の把握が上手く行われていなかったために混乱が生じてしまい、東北地方では電力供給ができない状態まで追い込まれたケースがあったそうですが報道はされませんでした。このようなに情報がうまく共有できていれば節電対策の大切さを理解することができ、尚且つ今後の地球全体のエネルギー消費を抑えていくことができると私は考えました。
宜しければSNSでのシェアをお願い致します!