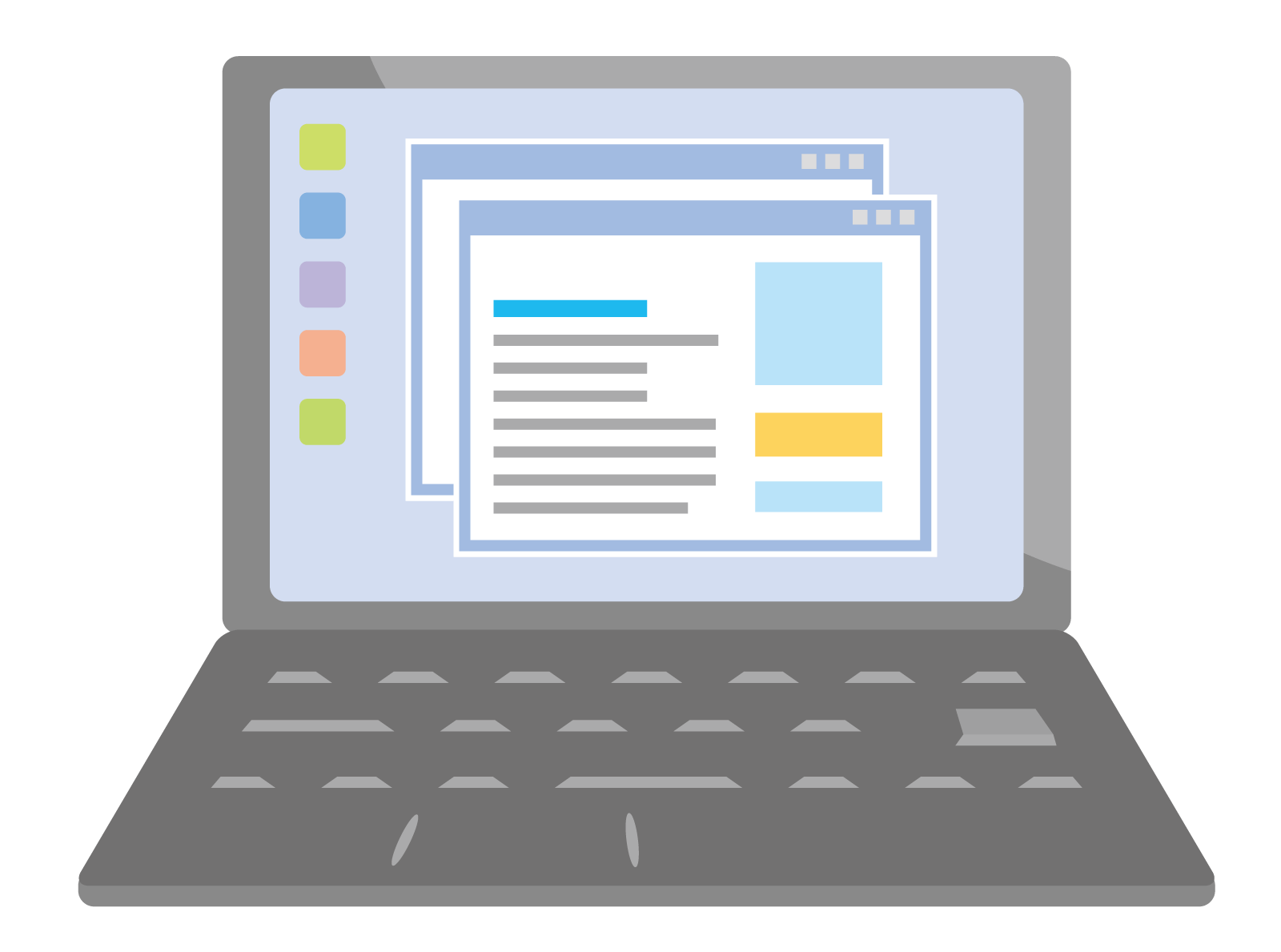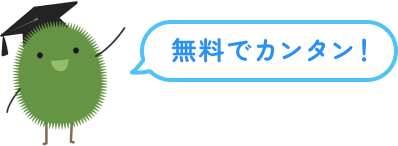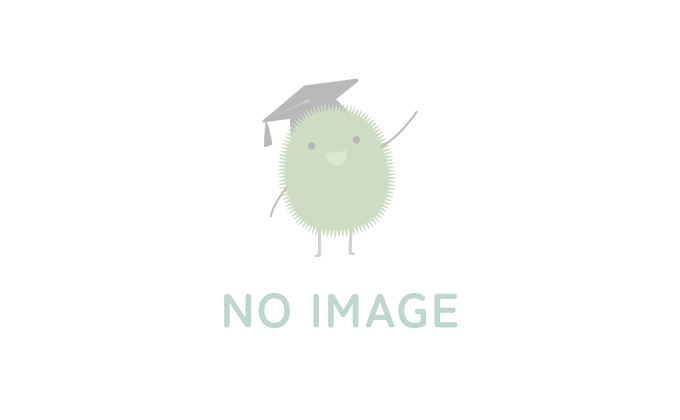- Home
- 家電の電気代一覧|ランキング
- パソコン
パソコンの電気代はどの程度?
パソコンの年間電気料金をご紹介いたします!
今日において、様々な企業やメーカーが作ってくれる便利な家電製品は、私たちの生活を毎日休むことなく下支えし続けてくれており、なくてはならない存在です。家電量販店だけではなく、Amazon等のオンラインストアにおいても、豊富な種類の家電をラインナップしていますので、複数の製品から簡単にご自身に適したものを見つけ、気軽に購入することもでき、とても便利な世の中になりました。
ただ、そうした便利な家電製品ですが、気になるのは電気代です。購入する際にも、どのくらいの電気代を支払い続ける必要があるのか、皆様ほんの少しは気になりますよね?そこで当サイトでは、各家電のカタログスペックに基づき家電毎の電気料金を算出し、その目安を皆様にご案内しております(家電類型別電気代DBはコチラ)。
本ページでは、「パソコン」にスポットライトをあて、利用する際に必要な電気料金や省エネ方法、また電力会社を切り替えた際の電気代削減額の目安等をご紹介いたします。特に電力会社を切り替えた際の電気代削減のインパクトは大きく、毎日の電気代をできる限り抑えたい方には非常におススメです(おススメの電力会社はコチラをご覧ください)。
パソコンについて
パソコンとは、パーソナルコンピュータの略で、個人利用を目的としたマイクロコンピューターのことです。今でこそ、パソコンはインターネットを使ってメールの受送信や情報を収集するためのツールとして活用されていますが、そもそもは演算機器として数値計算、情報処理などのために、アメリカが第二次世界大戦中に開発を進めた機械です。戦後、軍事機密とされていた演算機器の設計図を含めたノウハウが民間に公開されたことがきっかけとなり、パソコンの開発が一気に進められました。
個人が利用するためのパーソナルコンピュータが最初に登場したのは1970年代後半、アメリカのMITS社が開発したAltair8800だと言われています。その後、形や集積回路などハード面での研究がすすみ、実用的なものとして、スクリーン、キーボード、記憶装置が備わったAppleⅡが1977年に発売されました。
基本的にパソコンはそれ本体であるハードウェアと、パソコンに命令したり、パソコンと人間の仲介を担ったりするソフトウェアによって構成されています。ハードウェアは記憶装置、演算装置、制御装置、入力装置、出力装置の5つの働きを果たす装置で成り立っています。この5つがなければパソコンのハードウェアを満たしていないため、パソコンではありません。またここでいう記憶装置とは、各領域への命令を一時的に格納するための装置であり、過去に作成したファイルを記憶しておくことは出来ません。ファイルの記憶はSSDやHDD、USBなどの補助記憶装置を外付けで取り付けて行うことが一般的です。
ソフトウェアはオペレーションシステムとアプリケーションソフトの2つに分けることが出来ます。オペレーションシステムとは通常OSと呼ばれ、人間の命令をコンピュータが理解出来るように通訳する、いわば仲介役です。Windows、MacOS、UNIXなどがOSに当たります。アプリケーションソフトとは、表計算やワープロ、ゲームなど多機能にわたり、目的に応じた作業を可能にします。
パソコンの性能は、CPU、中央処理装置と記憶装置の容量の大きさで決まります。CPUとは、「制御装置」と「演算装置」を併せた名称です。パソコンの頭脳とも言える場所であり、1秒間に処理できる回数を表すクロック周波数によって性能を表します。頭脳の回転数とも言えるクロック周波数が大きければ大きいほど性能がいいパソコンといえます。また、メモリがあまりに小さすぎると同時に違う作業ができない、データが途中で消えてしまうなどの不具合が発生する可能性があるので、十分大きいものを選びましょう。
パソコンの電気料金の計算方法
基本的に、家電製品のカタログスペックの中には消費電力量に関する項目があり、この項目の数値を参照することで電気料金を算出することができます。大体の家電のカタログ表にはW単位で記載されており、例えば500Wの家電であれば、「500(W)÷1000×電気料金単価」の式により1時間当たりの電気代を求めることができます。
電気料金単価は電力会社により異なりますが、例えば「30.57円/kWh」であった場合、「500(W)÷1000×30.57=15.285円」となります。そのため、500Wの家電を1時間利用した場合の電気代は、15.285円となります。
それでは、この計算式をパソコンにも当てはめていきます。パソコンの場合、サイズや機能等により異なりますが、概ね45W程度の製品が多いため、パソコンを1時間利用した際の電気代は目安として「45(W)÷1000×30.57=1.38円程度」となります。利用時間別の電気代目安は下記表にまとめておりますので、ご参考ください。
| 利用時間 | パソコンの電気代 |
|---|---|
| 1分 | 0.02円 |
| 10分 | 0.23円 |
| 1時間 | 1.38円 |
| 24時間 | 33.02円 |
このような計算式を基本として、本ページでは「パソコン」のスペックを元に様々な角度から電気料金を算出しています。なお、特殊な電気の算出法となる家電につき計算の困難な製品については、経済産業省資源エネルギー庁による「省エネ性能カタログ」も参考にしながら概算値を求めています。
パソコンの年間電気料金
パソコンの年間電気料金は、概ね「1506円」となります(1日3時間、毎日使用した場合)。なお、家計全体における2024年度の平均電気代は月間で10027円、年間では120324円のため、パソコンの電気代は電気料金全体の1.25%程度を占めることとなります。
年間の電気代(目安):1506円
※1日3時間、毎日使用した場合
※30.57円/kWhとして算出
※2020年製の製品におけるスペックより算出
サイズ毎のパソコンの電気代
パソコンのサイズごとの電気代目安を表・グラフにまとめました。製品の傾向としては、もちろん製品によって異なりますが、サイズが違っても電気代はそこまで変わらない変わらない可能性があります。
| サイズ | 年間電気代 |
|---|---|
| 【サイズ小】10インチ | 1,506円 |
| 【サイズ中】11.6インチ | 1,506円 |
| 【サイズ大】15.6型ワイド | 1,506円 |
パソコンの省エネ方法をご紹介
代表的なパソコンの省エネ方法は下記の通りです。パソコンの使い方を見直すことで、毎日の電気料金を少しでも安くできます。電気料金の削減にあたっては、手間とコストのバランスが大切なので、全ての家電で省エネ手段を実施するのは大変かと思いますが、何らかご参考になれば幸いです。
- 使わないときは電源を切る
1日1時間利用時間を短縮した場合、節約になります。 - 電源オプションの見直し
電源オプションを「モニタの電源をOFF]から「スタンバイ」にすると節約になります。

弊社(RAUL)は2005年の創業以来、一貫して「エネルギー・環境問題」をテーマに事業を展開して参りました。現場での長年の下積み経験によって、電気/ガスをより身近に感じていただきたくたく当サイトを運営しております。